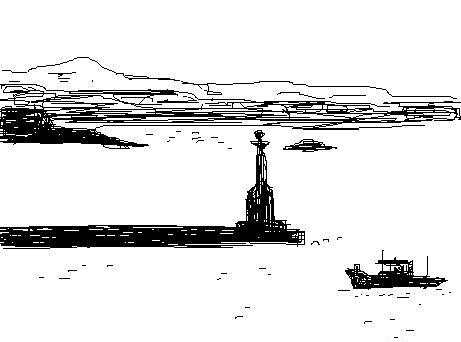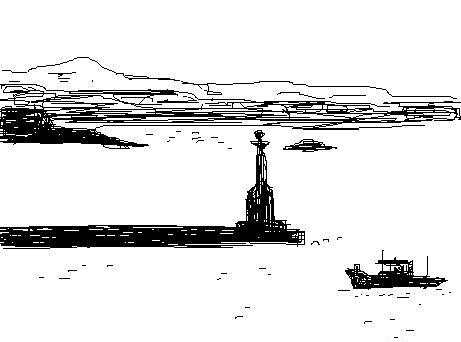初めてくらげを見たのは、伊豆の海岸だった。かれこれ15年も前になるが、当時僕はまだ学生で、東京の郊外にアパートを借りて住んでいた。ある夏の日盛り、都会を抜け出して潮風にでもあたりに行こうと海岸まで足をのばした。かたわらには当時付き合っていた恋人もいた。
海を渡ってくる風でいくぶんやわらいでいるとはいえ、真夏の陽射しはさすがに強烈で、僕たちはうなじを灼きながら、海洋公園の海岸線をたいした目的もないままぶらぶらと歩いた。会話はあまりはずまず、色白の彼女は紫外線による肌荒ればかりを気にしていた。首を小さくかしげながら困ったように笑うしぐさが美しい女性なのに、出合ったころに比べると、笑顔を見せることはまれになっていた。
玉砂利を転がしながら押し寄せる波に翻弄されるように、ぷかぷかと海面を漂う瑠璃色の不思議な生き物を発見したとき、元来好奇心の旺盛な僕は、興味を呼び起こされた。
それはピンポン玉ほどの大きさで、青をにじませた半透明の薄皮を半月状に膨らませており、風をはらみながら海面から突き出た岩の周りを行ったり来たりしていた。烏帽子にも似たその物体が、何かの生き物であることに違いはないようだったけれど、その造形がもつ美しさは僕の知識と想像の範疇をはるかに超えていて、その正体については皆目見当もつかなかった。
「何だろう?きれいだね」などと云いながら、僕は波打ち際に歩みこんだ。得体の知れないこの生き物の存在が小道具となって、ひょっとしたら固く閉ざされた彼女の心になにかしら変化をもたらすのではないか、そんな期待をしていなかったと云えば嘘になる。
ゆらめく水面に恐る恐る手をのばし、いぶかしむように摘み上げる。するとまるで根を生やしていたかのように、水面の下から撚った髪の毛を思わせる長い触手があらわれ、それは僕の手首にとりすがった。今から思えば気のせいに違いないけれど、風でへばりついたというのでなく、そこに物体の意思がはたらいたかのように感じられたのだ。次の瞬間、火箸をあてられたような強烈な痛みが腕に走った。「うっ」と唸ったまま、僕は慌ててその生き物をふりはらった。
蚯蚓腫れになった患部をかばうようにうずくまると、「大丈夫」と云いながら彼女が駆け寄ってきた。隣にしゃがみこんだ彼女は足元が濡れるのもいとわない様子で、その真剣なまなざしに触れたとき、ひょっとしたらまだやり直せるのかなと、僕はまったく場違いなことを考えていた。
空に放られよりどころを失ったその生き物は、風に流されながらやがて黒い岩肌にへばりついた。セロファンのようにつややかだった薄皮は、水面の浮力を失ったせいで、祭りから日が経った風船のようにだらしなくしおれていた。憎悪で色さした目に、それは少しも美しい代物ではなかった。
形からは推測もできなかった生き物の正体を、僕は痛みとひきかえに知ることとなった。
毒のある生物など、それほど沢山はいないだろう。これが世にいう電気くらげに違いない。そんな確信がにわかに芽生えていた。
家に戻ってから、さっそく本棚で埃をかぶっていた海岸生物の図鑑をひっぱりだした。「刺胞動物」でくくられた項目をためつすがめつ眺めると、確かにそれはいたのである。標準和名は「カツオノエボシ」。いわゆる群体クラゲと呼ばれるもので、それぞれ役割の異なる小さな個体が沢山集まっているため、あたかも一つの生命体のように見えるということであった。図鑑には、毒が強いので気をつけるようにとも書かれていた。
「謎の生物の正体がわかったよ」
台所で料理を作る彼女の背中に向けて、覚えたての知識を得意になってそらんじた。
「やっぱりくらげだったのか。毒があるならもっと早く教えてくれよなあ・・・」
誰に向かってというわけでもなく、ひとりごちた。
英語では「ジェリーフィッシュ」、漢字では海の月と称されるくらげのおおまかな形について、むろん人並みの知識はもっていたつもりだった。中には毒を持つものもいて、ときおり海水浴客などに悪さをするのだということも知っていた。それにもかかわらず、不用意に手をのばしてしまったのは、ほんの一瞬のことではあるけれど、その不可解な生き物がもつ美しさに、危険を回避する能力が麻痺してしまったからに他ならない。それは、僕が絵で知るくらげとはあまりにも大きくかけ離れていた。
「やっぱりさ、海の生き物って面白いよね。俺、世界中の海を渡り歩いてもっといろんな生き物たちを見てみたいなあ。」
玉ねぎを刻んでいた彼女の手の動きが止まり、小さなうりざね顔がこちらを向いた。
「今日の夕飯は肉じゃがだけだけどいい?月末で私もあまりお金がないの。」
小さく肩を震わせながら、感情を押し殺した声で云う。
まるで噛みあおうとしない会話は、こじれた二人の関係そのものといってよかった。せっかくの話題をはぐらかされてしまい、僕は軽い苛立ちをおぼえた。こちらの感情などお構いなしといった感じで、彼女は「それから」と言葉を続け、一瞬云いよどんだあと、決心したように口を開いた。
「昨夜実家の母から電話があったわ。毎月十分な仕送りをしているはずなのに、どうしてそんなにお金がなくなるのかって。母は勘の鋭い人だから、なんとなくあなたの存在に気がついたみたい。」
そう云ったなり、足元に力なく視線を落とした。
彼女の一言で、僕はたちまち現実に引き戻された。言葉の接穂さえ見つけることができず、唇をかんだ。彼女の母親が抱いた危惧は、実にまったくそのとおりだった。いつの頃からか、二人で使うお金のほとんどを、彼女が支払うようになっていた。僕はいつもお金がなく、暮らしがかつかつだったのは本当だけれど、それをいいことに彼女に甘えていたのも事実だった。自身すら養うことができないくせに、ろくすっぽ努力もせず、そのくせ夢のようなことばかり口にしたがる軽薄な男に振り回されている今の生活を、なんとかしてしまいたいのだという彼女の切実な思いは、こわばらせた頬が言葉よりも明瞭に伝えていた。
僕はうちしおれ、自分自身に対する嫌悪感に押し包まれながら、やっとの思いで「ごめんな」と口にした。
読みさしの生物図鑑は、すでに用をなさなかった。付箋がわりの人差し指を離し、図鑑を本棚に戻した。カツオノエボシの属名フィサリアには、「風でふくらませた袋」という意味があるという。それを彼女に話して聞かせようという気持ちは、もはや消えうせていた。
 |