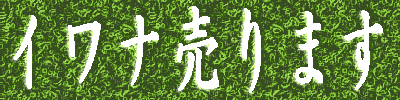 |
 |
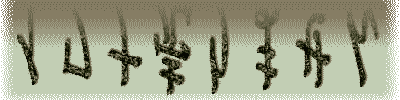 |
 |
| 河崎 徹 | |
| 河崎さんは、金沢近郊の医王山(いおうぜん)で、イワナやヤマメなどの養殖と、川魚料理の店「かわべ」をやっている、そろそろ落日の五十代。仕事より、魚釣りやら草野球やらにうつつを抜かし、店の方は、気が乗らないと勝手に閉めてしまうのが玉にキズ。(でも料理はウマイんだな)。いつもマイペース、ままよ気ままの行きあたりばったりエッセイからは、その人柄が伝わってきます。 |
|
| 第十三回 「今だから言える学校の悪口(数学)」 |
落語『親の顔が見たい(現代版)』の一節、学校のテスト(算数)で「五十四個のリンゴを三人で平等に分けるにはどう分けたらいいでしょう。」という問題でムスコの答え「それを全部ジュースにしてコップに分ける」、するとそれを聞いた教師は「どうもお宅のムスコさんには少々問題がありますね。」と。親「それでよし。さすが我がムスコ。ただしそれでも八十五点、残りの十五点は五十四個のリンゴをジュースにする手間ヒマを考えたら非現実的である。」と。 落語はそこまでとして、それでは現実的に五十四個のリンゴを平等に分ける(小学生に納得して)事は可能であるか。答えはNOである。なぜなら、リンゴ一個の大きさは違うし、リンゴの良し悪し(おいしさ)も違う。 そこで私の答え、とにかく子供達の五感にしたがい三通りに分ける。まず目で見て量を三通りに分ける。(これは大小があるから必ずしも数は3/1ではない。)そしてニオイを嗅ぎ、触ってみて、たたいて音を聞き、できれば少しかじってみたりもする。ただし、それでも平等とは言えない。そこで三人でクジ引きをする。勝った者から自分の好きなものを取る。これが私のいう三人で平等(に近い)な分け方である。 人類が集団生活をするようになった長い歴史の中で、ものを分け合う時に自分達の身についた五感を働かせてうまく分け合い、その後はクジ引き(運、不運)にまかせる。たぶんこの方法は、人類の歴史で数学(算数)なるものが生まれる以前から使われていた方法であり、又将来にわたってもこれ以上の方法はない、と私は思っている。 私の父親(故人)は、私に似て(逆か)仕事より遊びが好きな人間で、毎日のように魚獲り(船で夜、川に出て大きな網でフナ、コイ、ウナギ等を漁る)に出て、帰ってくるのは夜中であった。その魚獲りは船も網もオヤジのものであり、準備もオヤジが全部やっていたが、最低三人の人間が必要であり、漁れた魚はその人数で平等に分けていた。(そこだけがオヤジのエライ所だと思っていた。)その漁れた魚を人数分で割って平等に、といっても魚の種類も大きさも違えば、みんなのほしいと思っているウナギも一匹だけの事もある。それで、だいたい均等に分けて、後はクジ引きをして順に自分の好きなものを持っていった。その当時(小学校四、五年生の頃)はまだ食糧難の時代で、それぞれの人にとっては貴重なタンパク源であった。そのクジ引きを私がオヤジにかわって引くために、夜中まで必死になって起きていた。クジ引きは人数分のワラを用意して、一本ずつ長さを違えて長いのを選んだ者から自分の好きなものを取る事ができた。その時の緊張感が何とも言えずドキドキしながらクジを引き、自分のほしい「コイ、ウナギ」を手に入れた時のうれしさは今でも覚えている。 話しは変わるが、何年か前、時節は丁度秋、この里山では一番イイ時節、周囲をながめながら車を運転していたら、一人の子供が道路をフラフラしながら歩いていた。よく見ると近くに住む小学生で、何やらブツブツ言いながら歩いている。親が変な宗教に凝っていたかな、と思ったがそんな風でもない。道路を大型トラックが通るので、とりあえず車を止め「ボク(小学生)、どうした。家の近くまで乗っていくか。」すなおに乗ってきたのですぐ車は走り出した。でも子供は相変わらず下を向いてブツブツ言っている。よく聞くと、それは算数の九九を言っていたのである。聞けば、だいたいスラスラ(九九)言えるのだが、途中でつかえる事がある、と。特に六×九が苦手でまちがえるのだと。(今ごろはロックの好きな高校生になっているだろう。)六×十は六十、それはすぐわかる。だったら、それから六を引けばいい。でもそれではたぶん、学校側(教師)が満足しないだろう。水の流れるようにスムーズに言えなければ。 またまた話しは横道にそれるが、我が家の長女が小学校低学年に九九を習い始めた頃、やはり毎日そればかりだった。家(当時娘は転校したばかりで、私と二人の生活)では、ゆっくりだと九九はマスターできていると思っていた。しかし、学校(教室)では、まったく不完全であった。ある日、授業参観に行って教室に入った私がまず目にしたものは、算数ドリルと称される九九の練習帳で、その同じ問題を自分で何度やったかを示すシールが個々人の名前の上に貼られており、我が家の娘は一枚か二枚で、他はみんな十枚以上であった。さらに授業では教師が九九の何々と言ったら、生徒はみんな間髪を入れずに一斉に手を挙げスラスラ答え、教師も参観に来ていた父兄も、そして当の本人も三者とも満足気であった。我が家の娘もみんなにつられてしぶしぶ遅れて手を挙げていた。どうせそんな生徒には教師も指名しないだろうと、何の期待も持たずに授業をながめていたのを覚えている。 その頃からクラスで長女がいじめられるようになり、学校(担当の教師)から電話があり、「子供は勉強のできる子供はいじめたりしないから、お父さんが家で九九(勉強)を見てやってください。」との事。「何で勉強ができなからと言っていじめられなければいけない。」と返事をしたが、わかってもらえなかった様だ。 戦前、戦中の教育では、クラスで教育勅語なるものをみんながスラスラ言え、中にスラスラ言えない者がいると、やはりみんなからいじめられたと聞いた。何でもみんなと同じペース、それも間髪入れず速く、のクセが教育の世界でも直っていない様だ。 ようやく話しをもとにもどそう。たしか五十四個のリンゴの話しだったと思うが、毎日々々掛け算、割り算など何度も時間をかけ、完璧にできるまでやるのが小学校(中学校)では一番大切な事だろうか。(掛け算、割り算が不要だとは言わない。)小中学校(義務教育といわれる年代)に必要な事は、自分の持って生まれた(誰もが持っている)感性(五感)で、人間という集団の中で自分という個人が生きていく基本的なものを身につける事であり、学校(教師)や国家の期待に答えるためのものではない。ましてや受験に備えるためのものでもない。五十四個のリンゴを三人で分けるのに、すばやく「五十四÷三=十四」と答えた所で、それは単なる目安でしかなく、実際はそんな事だけで三人は納得しないだろう。リンゴの大きさ、質がそれぞれ異なる時に、それではどうすればいいか(納得できるか)、という答えは私が言った自分達が持っている五感と、それをさらに研ぎ澄ます経験だと思う。毎日々々掛け算、割り算を完璧にやるヒマ(時間)があったら、いいリンゴ(おいしいリンゴ)の見分け方を学び(今の教師にはできないだろうが、その時は農家の人に教わればいい)、又そのリンゴがどの様にして生産されるかを学び、食物の大切さを感じる事の方が大切である。 今の社会、お金さえ出せば安全で美味しい食べ物が手に入ると大人も子供も思っているが、こんな時代がいつまでも続くとは思わない。いい野菜の、いい魚の、いい肉の…、と自分で見分ける力となると、日本の子供(いや大人も)世界の最低レベルであろう(学力はトップレベルだそうだが)。エラそうな事を言う私も魚以外はまだまだ(未だにリンゴの良し悪しもわからない)である。 受験の時に「たぶん私の将来に何の役にも立たないであろう(例えば微分、積分)」と思いながらやっていたあの貴重な時間、あの当時やりたい事がいっぱいあった(暗い青春時代)のに、惜しい事をしたものだと思う。微分、積分はあれからこの年になるまで私の人生には「かすりもしなかった」が、数学(計算)がそれを使う人の意図でどうにでも利用されるという事は学んだように思う。 ある有名な生物学者は、世界の人口(数)と食料の総生産量をコンピューターではじき出し(計算し)、その数字から食糧生産が人口増加に追いつかないから貧しい(アフリカ、アジア)人々の人口増加を抑えろと主張(後進国の貧困が原因)している。一方、ある作家が「世界がもし100人の村だったら」とした文章の中で、やはり世界は食糧難であると。ただし、今の日本などの一部の先進国が世界中の食料を買いあさり、多くの貧しい国々が食糧難で苦しんでいる。先進国が食糧難の原因だと。同じ「世界の食糧難」に関してもまったく逆の見方があり、それぞれの思惑によって数字(計算)が使われている。一方は優秀(競争で勝っている)なものが多くを取るのは当然、もう一方はできるだけ平等に、という考えである。残念ながら今の社会(世界)は、前者の考えで成り立っており、最近では世界の諸問題を考える時には、勝ち組=アメリカがすべてという感じで、平等などという言葉自体がもう死語になりつつあり、こういう文章を書いていて段々白々しい気になってくる。 「物(リンゴ)を平等に分けるにはどうしたらいいでしょう。」などというのは、落語の世界(笑いの世界)だけになってしまいそうだ。 |
| 第十二回へ |