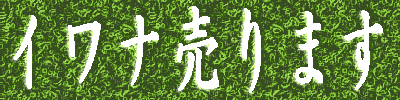 |
 |
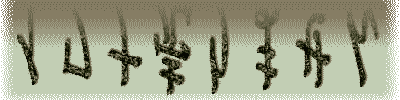 |
 |
| 河崎 徹 | |
| 河崎さんは、金沢近郊の医王山(いおうぜん)で、イワナやヤマメなどの養殖と、川魚料理の店「かわべ」をやっている、そろそろ落日の五十代。仕事より、魚釣りやら草野球やらにうつつを抜かし、店の方は、気が乗らないと勝手に閉めてしまうのが玉にキズ。(でも料理はウマイんだな)。いつもマイペース、ままよ気ままの行きあたりばったりエッセイからは、その人柄が伝わってきます。 |
|
| 第十七回 「なにわ芝居見学ツアー 前編」 |
私「今度大阪へ芝居を観に行く」 私の店の常連客「大阪なら吉本(興行)か」 私「いや大阪市の芸術創造館」 客「どんな内容?」 私「藤澤清造(石川県七尾市出身の作家、貧困と病苦の究極の私小説『根津權現裏』−藤澤製造貧困小説集(龜鳴屋刊)を残し、昭和七年冬流浪の果てに芝公園で凍死した)その彼が残した戯曲を地元の劇団(飛ぶ教室)が演じるとの事」 客「要するに貧乏人が書いた芝居を貧乏人が観に行くわけ? そんな自分の将来を暗示する様な芝居を観て、重たい気分で帰ってくるわけ? それより今(十二月)、お前の店の一番いそがしい時期(お歳暮シーズン)やないか。しっかり働け。」 私「確かにいそがしい時期だけど、貧乏で、その上芝居を観に行くヒマもない(貧乏ヒマナシ)という理不尽な事はいやじゃ」 客「そんな事を言っているから、いつまで経っても貧乏なんじゃ」 私「放っておいてくれ! 行くと決めたら行く」 * 客の適切な指摘に一瞬たじろいだが、やっぱり行くと決めたら行く事にした。ただ、いよいよ明日行く、という晩、遠足の前日の晩のように、枕もとにミカン、チョコレート、週刊誌をそろえて早めに床についたが、客に言われた事がどうも気になる。「貧乏人が貧乏作家の芝居を観て身につまされ、面白くなかった」というのではつまらない。貧乏人が地位や金のある作品にケチをつける事には“快感”があるけれど、貧乏人同士でけなしあう事はやってはいけない事だろう。ならば、ここは何が何でも意義を持たさなければいけない(イラクへ自衛隊を送る決定をした小泉首相の心境)。 とは言うものの、私は子供(小学生)の頃から芝居というものを観た事がない(お金を出して)。いや、偏見があって観たくないと思っていた。小学生低学年の頃の学芸会で、出演者としての私の役は、大きなゼスチャーでおどろいて「おかあさま(おとうさまだったかも)」と一言いうセリフであったが、その一言がいえなかった。 当時の私は「かあちゃん(とうちゃん)」だったので、その「おかあさま」の一言がどうしてもいえなかったのである。 そのため、結局セリフのない役に代えられた。先生からも我が家の母親からも「なんでそんな一言がいえないの」とののしられ、私にすれば「できないものはできない」。そのため、ひどく傷ついて学芸会(芝居)=きらい、となってしまったようだ。 まあ、今回を機に、芝居というものを考え直してみるのもいいかもしれない。それと、先日読んだ『バカの壁 タイトル−人間は話し合えばわかり会えるというのはウソ』(私には、作者が何を言わんとしているのか今一つわからない=私がバカという事か)を読んで、私(一応生物学を専攻した者として)なりに感じた事は、人類は誕生から現在まで、まだまだ進化の途中=不完全(ただし完全とはどういうものかはわからない)という事だろう。さらに言葉(言語)なるものはできてから間もなくもっと不完全である。それ故言葉というものの限界でもある。だから本当に個人にとって重要なことには「言葉にならない言葉で言い表せない等々」である。楽しい時、苦しい時、悲しい時、それらの人生の経験を言葉だけで伝えるには無理がある。そこで言葉が出来る以前の意志伝達方法である体をつかった表現と、不完全ではあるが言葉を使ってよりわかりやすく意志を伝えようとするのが芝居だと思う(あまり自分の言っていることに自信はない)。ただしまだ不完全であり、不完全な意志伝達法しか持たない人間であると理解した上で、これでやっていくより仕方がない。それなのに、あまりにもこの人間(自分)というものを追いつめていくと「危ない世界−藤澤清造」に入り込んでいきそうだ(私にはできない=やりたくない)。 * さて、貧乏人をテーマにする意義については、先ほどの話とも重複するが、人類(日本人)が今の生活様式になったのは、ここ五〇年から一〇〇年ほどである。簡単に言えば、それまではほとんどの人が貧乏であった(これから先も保証はない)。それ故に貧乏がもとでのトラブルは日常茶飯事であり、むしろ今の様(今の日本の様)なのが不自然と言えるかも知れない。ただ今の私達のDNA(遺伝子)は貧乏な時のままである(DNAは急には変われない−私の実感)。生活様式がずいぶん変わった(豊かになった)様だが人間の中味は昔とさほど変わっていない。この肉体的にも精神的にも貧乏が基本の現代人が、美味いものを食い過ぎてやれコレステロールが高いとか、歩くのをいやがってやれ運動不足とか、もともと人間は歩き回って(運動して)必死になってエサ(食物)を捜していた(粗食の)生物である。またそんな生活での精神状態もやはりしっかり受け継いできている。そんな人間である(貧乏が基本)と認めた上でやはりどう生きるのかという事だろう。 * 以上、人間の本来の姿「不完全で、かつ貧乏」という人間の原点に立ち帰り、今回の貧乏をテーマにした芝居を観る、という意義付けができた。「よし、これで理論武装は完璧」(我ながらあきれるぐらい強引)と時計を見ると午前二時だった。 * 当日の予定、朝六時起床。私は仕事場に泊ったので寝過ごす危険があり、六時に勝井君より電話でモーニングコールあり。まったくの寝不足で、起こしてもらって言うのもなんだが、モーニングコール(今まで経験なし)は女性からのものと思っていたので、思わず無愛想に答えてしまった。集合場所(勝井家)に着くや否や、彼から「お前の電話の対応は仕事の時と同じ無愛想やな」と言われてしまう。 今回の「なにわ芝居見学ツアー」の一行は、ヒマがあっても金のない私(養殖業兼山菜川魚料理店)と、本はあっても金のない出版業(龜鳴屋)の勝井夫婦、金があってもなくてもいつも酒を飲んでいる庭師(庭師、教師、ペテン師は同類と言って憚らない)の丸銭さんと二人の娘さんの合計六人である。中年男性三人はいずれも今回の芝居のテーマ「貧乏」とは少なからず縁のある人達である。特に丸銭さん曰く「貧乏を語らせるなら、わしは誰れにも負けん」と豪語(?)している。この合計六人が金沢駅から大阪駅行きのバスに乗り込むことになっていた。 * 丸銭さん本人だけが先に金沢駅に着て待っているとの事だったが、五人のグループが駅に着いたが姿が見当たらない。娘曰く、「ホームレスの人とよく似た人を捜して」と言われ、まもなくそれらしき人を見つけ全員無事バスに乗り込む。バスは二階建てで眺めは良かったが、少々窮屈な感じがした。それでも途中ドライブインで休憩もあり(ただし他のバスも沢山停まっていたので自分達のバスがわからなくなる心配があり、あまりバスから離れられなかった)。バスは順調に走り、雪の少し残る日本海岸から「長いトンネルをくぐり抜けるとそこは晴れ」の景色に変っていった(トンネルを抜けるとそこは雪国だった、というのは私達雪国に住む人間には、それのどこがいいのかわからない)。思わず私「毎日こんなにイイ天気だったら朝からでも労働意欲が沸くだろうな」 みんな無言で窓の外を見ている(しらけた感じ)。私「もっともわしの場合は朝からでも釣りに行くかもな」と、それでもみんな無言で窓の外を見ている(その通りといった感じ)。 * バスはほぼ定刻に大阪駅に着く。そこから会場のある千林大宮という所まで地下鉄に乗るため地下街を唯一大阪の地形にくわしい丸銭の娘さんにくっついて歩いた。地下を歩いていると今自分がどこにいるのかわからなくなる。それにウロウロ歩いていると周囲の人達(大阪の人)は早足で次々と追い越していく。それだけで疲れてくる。年寄り二人(私と丸銭さん)がだんだんみんな(四人)から遅れ気味となる。そのうち丸銭さんが「耳鳴りがする」と言い出した。私も「なんで地下ばかり歩くんじゃ、モグラじゃあるまいし」と二人ともブツブツ言いながらついていって、ようやく地下鉄に乗り千林大宮の地下の駅に着いた。駅の自動改札口(私にとっては初めて)で切符をそこに入れようとしたが、ポケットから出てきたのは、どこかのスーパーのレシートだけ。周りにだれも見ていないので「これでもいいか」とそれを入れて外に出ようとしたら「バタン」と扉が閉じてしまった。「なんだ、この扉は。ヒト(私)に一言のことわりもなしに実力行使に出るとは失礼な」と思ったが、みんなが心配そうな顔をして外で待っていたので、必死に切符を探してやっと外に出してもらう。私「一言ぐらい言えよ。ここの地下鉄の愛想悪いのはかわべ(私の店の屋号)と同じやな」、丸銭さん「そやそや」。ようやく地上に出てほっとする。 * それから開演まで時間があったので、どこかで昼食を取る事にする。このあたりは市の郊外で金沢の市街地を歩いている様な感じで、大きな建物もなく、目についたのは税務署ぐらい。その近くに食堂があったが、「雰囲気が悪い」という事で少し離れた「大阪名物うどん」の店に入ることにした。丁度昼時で客で満員だった。それで店の外の長椅子に腰かけてしばらく待った。天気の悪い金沢では考えられない事であり、それがかえって面白かった。やがて、店の中に入れてもらえ、注文をする。丸銭さんがすぐ「ビール」と言う。彼の娘さん「お父さん、大阪で飲んでも、金沢で飲んでも、同じものをわざわざ大阪まで来て飲まんでもいい」、それでも彼は「ビール」を注文する。私は「ここの名物は何ですか」と聞くと「タマタマうどんです」と言うのでそれを注文する。他の何人かもそれを注文した。やがて出てきたのは、太目の温ついうどん(汁なし)の真中に生タマゴ一個割ったのが乗っているだけ。店員さん「生醤油を少々かけ、箸で卵をくずして食べてください」 メニューには「大阪のうどん通の食べ物」と書いてあった。温ったかい太目のうどんに生タマゴをかけて食う。私が自分の店でよく昼食に温ったかい御飯に生タマゴをぶっかけて食う「タマゴ御飯(手抜き御飯とも言う)」の御飯のかわりにうどんになっただけ。いや、だけと言ったら通の人に叱られるだろう。事実他の人は「うまい、うまい」と食べていた。私もうどんはうまいと思ったが、わざわざ大阪まで来て「タマゴ御飯風タマタマうどん」ではと思うと、少々さみしい気分になってしまった。「もう二度と来れない大阪(少々オーバー)だからもっと…」と思ったが、「食い物にはグチを言わない」という私の信条だから「うどんはうまかった」と外に出る。 * それから、まだしばらく時間があったので、近くの感じのイイ喫茶店でひと休みする。私はそこでコーヒーを注文する。丸銭さんはまたも「ビール」。実は私、ここで濃いコーヒーを飲まないと芝居を観ている途中で寝てしまいそうな気がした。丸銭さんの娘さん「お父さん、絶対よっぱらって芝居の途中で寝てしまうから」。コーヒーでもうろうとした頭を何とかしようとしている私、もう完全に出来上がってしまった丸銭さんの年寄り二人と頭も体もまだ元気な四人は会場へ向かった。 * 後編に続く |
| 第十六回へ |