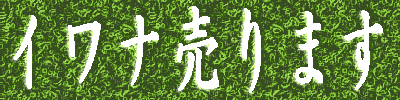 |
 |
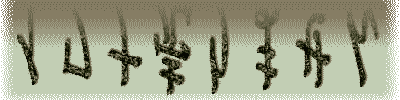 |
 |
| 河崎 徹 | |
| 河崎さんは、金沢近郊の医王山(いおうぜん)で、イワナやヤマメなどの養殖と、川魚料理の店「かわべ」をやっている、そろそろ落日の五十代。仕事より、魚釣りやら草野球やらにうつつを抜かし、店の方は、気が乗らないと勝手に閉めてしまうのが玉にキズ。(でも料理はウマイんだな)。いつもマイペース、ままよ気ままの行きあたりばったりエッセイからは、その人柄が伝わってきます。 |
|
| 第十八回 「なにわ芝居見学ツアー 後編」 |
大阪市立芸術創造館(大阪のイメージに似合わない名称−失礼)、やっぱり吉本の方がよかったかな、と思いつつ若い人達に従って劇場の中に入った。 「百人ぐらいかな(私はなぜか映画館などに入るとすぐ人数を数える−野鳥の会会員ではない)」と思われる人達が静かに開演を待っている。見やすい会場の中ほどの席を取る。隣りが丸銭さんである。それが別に不満な訳ではないが、とにかく酒くさい。「まあいいか。横のおっさん、私と無関係」という態度で席に深くこしかけて眼をつむっていたら、ハッと気が付いたら一瞬だが眠っていた。丁度運転中に一瞬だけ眠ってしまった様な気分で、この先どうなるのだろう(寝てしまう)と急に不安な気持ちになる。 * やがて開演となり、何がはじまるのだろうかと舞台(昭和初期のタタミ敷きの小部屋)を食い入る様に観ていると急に天井から出刃包丁が落ちてきて、その小部屋の片隅のタタミに突き刺さったのである。 私「すごい。これは(これをやっているのは)本職の包丁人(料理人)か、本物のヤクザにちがいない」と感心する。 そこからあやしげな男女のやり取り(会話)がはじまり「お前が悪い」「アンタが悪い」とけなし合いで本当に悪いのは男で一幕が終わる(いつの時代も男はダメな様だ)。部屋の片隅に突き刺さったままの出刃包丁、男女の憎悪のあげくの果ての出刃包丁、なるほどなあと感心する。 * 二幕は更にどうしようもない男の登場。だんだんとそのくだらない男に腹が立ってくる。「早くそこの出刃包丁で刺し殺せ」と思ってしまう(勝井君に言わせれば、観客にそんな思いをさせる事ができれば役者冥利につきる、と後で言っていた)。二幕終了。どうもアクの強い料理を食い過ぎて「もう沢山、もう満腹」という感じで、急に眠気が襲ってきた。それでも「せっかく大阪まで来たのに」と思い、必死になって起きていた(つもり)。 * だが三幕目(三幕が最終)が終わった時点で、芝居の内容は頭の中にほとんど残っていない。正気にもどったのは、芝居が全部終って劇団員全員が観客に向かって挨拶をして、座長が「藤澤清造−貧困小説集の出版者勝井さん一行六人が金沢からわざわざ来られて…」と紹介された時だった。「しまった。やっぱりわざわざ招待されたのだから寝るんじゃなかった」と思ったが後の祭り。最後に座長が天井から落す出刃包丁の裏話をされた。「劇団の男性がやってみたがみんなうまくゆかず、ちなみに女性団員がやったらうまく刺さった」と、私「なるほどな、藤澤清造にこの話をしたら『アタリマエ』と言うだろう」。 室から出た所でこの芝居の企画に関わった小堀さん(縁あって知り合い)に出会う。彼に芝居の感想を聞かれて「寝てました」とは言えないので、私の方から先に「あのろくでもない男に足げりされていた女性の役者さん、大変ですね」と言ったら、「体中アザができています」と、「そんな痛い思いをしてまで芝居をやるの」とは言わなかったが「金になる訳でもないのに体にキズをつくってまで…」と思ってしまった(そうゆう私も日ごろから「お前のやっている事は理解できない」と言われ続けている)。やはり子供の頃の芝居=キライのせいだろうか、どうも出かける前に理論武装して出かけて来たものの、結局は「眠気」と必死に戦っているうちに芝居が終ってしまった、という感じだ。そしてあの出刃包丁だけがやたらと印象に残った(私もやって(天井から落す)みたかった)。 余談になるが、私の横に居たよっぱらい=丸銭さんは芝居が始まって間もなく退席して、終盤になって席に戻ってきた(アルコールの補給に行っていたのか、居眠りに行っていたのか、はたまた、芝居のないように己の身につまされて耐えられなくなったのか)。 劇場から外に出ると、もう少し暗くなりかけていた。誰れが言うでもなく「あの芝居(内容)は大阪でなくてもどこにでも(内灘、金沢)ある話だ。」、丸銭さんの娘さん「内灘とまで言わなくても我が家そのもの」と、本人(丸銭さん)「その通り」。おそろしい親子である。 * 帰りは来た時と同じで、地下鉄に乗り(今度は丸銭さんが改札口で止められた−本当に機械というのは融通がきかない)、大阪駅まで行き、そこから電車に乗って帰る事になった。日曜日の夕方の大阪駅、とにかく人が多い。発車まで時間があったので、地下デパート(阪急)でお土産と弁当を買う事になった。 地下でありながらこの人の多さはどうだろう。きっとアリの巣(土の下)の有り様を拡大したらこんな様子だろう。ちょっと油断すると迷子になりそうだ。左手でポケットの中のサイフを握りしめ、右手はいつでも丸銭さんの娘さん(地下街にくわしい)のソデ(腕)をつかめるようにして、必死に後についていく(もう入園前のガキと同じで自分が惨めになる)、だんだん買い物をする意欲がなくなっていく。そのうち丸銭さんが「息苦しくなった。早く出よう」と言ったので、二人はデパートの出口まで来て、立ち止まっても他人(ヒト)にぶつからない空間を見つけて「ホッ」とする。「これが大阪の活気というものか」と二人で話していたが私に言わせれば「これは五〇年前(終戦直後)の闇市の光景(映像で観た)に見えた。客の服装、店の構え、販売品を取り替えれば、やっている事はあの当時と変らない(忙しすぎる。本質は昔のままの貧乏人である)」 * 捨て台詞(大阪人は貧乏人)を残して、ようやく列車に乗り込み、一同ほっとする。私は買ってきた弁当を、丸銭さんはまたまたビールを飲み始めた(もう娘さんは何も言わない。あきらめてか)。他の人達(四人)もさすがに疲れたのか静かに席に座っている。私も久し振りに乗った電車の窓から、暗やみの中に時々灯りがついては消えていく(通り過ぎていく)外を眺めていた。フト、その窓ガラスに横に座っている丸銭さん(酔っぱらい)の顔が映った。その顔が「藤澤清造とはたぶんこんな雰囲気を持った男だったのでは」と思った。いつも片手に酒を持ち、言葉は暴力性がなければいけないと言っては敵を造っている。昔は文学青年(今は酒を飲んだ時だけ文学青年、いや文学老人)、父親の世代は内灘闘争で全国中にその存在(内灘)を知られ、本人達も青年時代、内灘火電反対闘争で火電(電力会社)を追い出した。その先頭に立って「内灘の事は自分達が決める」と権力と闘ってきた男である。「ただ酒を飲みすぎる…」と私は言いたい所だけれど「お前にだけは言われたくない」と言われそうなので言った事はない。方や、今まで本を造って「儲かった」という言葉を聞いた事のない出版業の男(勝井君)、「商売が自分に合っていない」と言いながら(わかっていながら)何十年もやっている男(私)、いずれもあと一歩うまくゆけば社会的地位(?)のある人でいられたかもしれない−あと一歩落ちれば藤澤清造(貧乏の果てに凍死)である。 昼間の仕事や遊びで疲れ果てた人達が、ホッと一息ついている夜行列車の車内の雰囲気、そして、ついては消えていく外の景色を眺めていると、物事の判断が冷静になれるのだろうか。 あれこれ思いを巡らせている内に金沢駅に着いた。もう真夜中近くである。駅から外に出ると、この北国にはめずらしく晴れていた。その分だけ冷え込んでいる。片隅に何人かのホームレスの人達がいた「凍死なんかするなよ。生きていればそのうちいい事もある(だろう)」。 自分(私)の車が止めてある場所(勝井宅)まで歩きながら考えた。「客に芝居見物はどうだった、と聞かれたらどう答えようか。そうだ。大阪駅まで2階建ての豪華なバスで行き、大阪人の通が食べるタマタマうどんを食べ、芸術創造館で芸術性あふれる芝居を観て、大阪の活気あふれる阪急デパートで買い物をして帰ってきた。大変有意義な一日だった」と言っておこう。 |
| 第十七回へ |