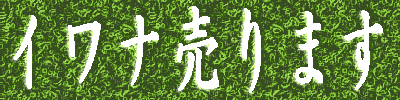 |
 |
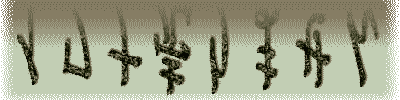 |
 |
| 河崎 徹 | |
| 河崎さんは、金沢近郊の医王山(いおうぜん)で、イワナやヤマメなどの養殖と、川魚料理の店「かわべ」をやっている、そろそろ落日の五十代。仕事より、魚釣りやら草野球やらにうつつを抜かし、店の方は、気が乗らないと勝手に閉めてしまうのが玉にキズ。(でも料理はウマイんだな)。いつもマイペース、ままよ気ままの行きあたりばったりエッセイからは、その人柄が伝わってきます。 |
|
| 第三十一回 「この冬の終り」 |
私がこの仕事(養殖業)をはじめた三十数年前、前任者が建てた家と池があり、そこは前任者がやめて十年以上もの間使用されていなかった。それを、私と無報酬で手伝ってくれた人達で、池、家共、それなりに直して今日に到っている(もう、あちこちガタが来ている)。 その家の方の話しだが、あちこち直して住めるようになったのだが、出窓があり(そこから村全体が見渡せる)、そしてそこに障子が入る構造になっていた。しかし、その障子戸がどこかへ行ってしまってなく、仕方なしにあちこちの古道具屋をあたって、ようやく十枚の障子戸を集めた。ただし、木造のつくりの家の障子戸というのは、皆、その家にあわせて建具職人がそれぞれ造るもので、十枚集めてもピッタリ合うものは一枚としてなかった。それを一枚づつ微妙な細工で直すのは、私の最も苦手とする所だったので、しばらくは(数年間)障子戸なしで過ごした。しかし、障子戸が入る場所に障子がないのはどうも物足りない感じがしていた。私の周りには器用な人が多く、それぞれサイズの合わない障子戸をうまくクギを使わずに調節し、障子紙も全部張ってくれた。それだけで室が見違えるような和室となった。 障子が映えるのは、やはり冬である。ここに住むようになってから、かねがね「冬、障子が入った室で火鉢(親類の木材商からもらった立派な長火鉢)に手をかざし、昔風の足の細工が凝った机に座って、文章を書く」それはたぶん教科書かどこかで見た有名作家の執筆活動の姿で、それを一度やってみたかった。「たぶん今夜は大雪になるだろう」と思われる日、早目に仕事を終らせ、長火鉢に炭をくべ、五徳の上に鉄瓶を乗せ、もう絶対に外部の人が入って来ない時間帯となり、深閑とした室に一人座った。 どこかで何か物音がしそうな気配を必死に消そうとするのが雪の降る音であり、その事を深々と降る雪というのだろう。障子の向うでその気配がある。そのどこか重々しい空気がスーッと途切れる事がある。たぶん、その時は雪のやんだ時だろう。 空のかなたから、この家をすっぽりつつみ隠すのに降らせた雪を「予定通り事は運んでいるだろうか」と一時(いっとき)仕事をやめ、その出来具合を確かめ、また降らし始める。こっちも、それに答えるため、じっと身をひそめる。たぶん明日朝までにこの家は雪にすっぽりおおわれるだろう。 その時気が付いた事は、窓と室との間の出窓に、たかが障子紙一枚が窓の隙間から入り込む風と冷気を遮断してくれ、雪の降る気配まで何となく感じさせるという、すばらしい昔の人の知恵を知ることとなった。障子という防音装置の効いた室、聞こうとすれば聞こえるし、そうしたくない時は、まったくの静寂を作り出してくれる雪、これだけ感激した夜だったが、その時、何を書いたのか全く覚えていない。 降り積もる雪に 埋もれていく自分 もう古い話しだが、私達夫婦は結婚当初から別居(今は一緒に住んでいる)して、神奈川県と石川県とにそれぞれ住んで、毎週、そこに行き来していた。私の方からは仕事が終ると夜行列車に飛び乗り、翌朝早くに上野駅に着き、それから小田急線に乗り換え、目的地に向かった。朝早く上野駅に着き、眠たい目をこすり列車から外に出ると、いつもいやな気分になっていた。駅の構内は列車から吐き出された生暖かい空気と排気ガスの臭い、それと前日のヨッパライがもどした様な汚物の臭い等で、急いで外の空気を吸いたくて出口に向かうが、そこにも前日の残骸がそのままあり、そこを大勢の人が流れていく。自分の行きたい場所(ホーム)に行くのにも一苦労であった。その時、これが都会の朝か、と思った。私にとっての朝というのは、前日あった事が夜という時間で区切りがつき、新しい一日が又始まるもの、と思っていた。しかし都会では朝は夜の延長でしかなく、前日からドロドロしたものがそのまま続いているという感じだった。 私の様なナマケ者には、一年には四季があり、一日には朝と夜があるから、それに合わせる様にしてかろうじて生活している。 ところでこの文章を書いている今年の今、現在(二月二十六日)(六十数年前の東京は大雪だった)、周囲の山々にも雪はない。そう今年はやはり冬はないままで終りそうだ。雪が溶け出す今頃、「そろそろ春だ」と雪からガラス戸を守る板を取りはずし、「いよいよ釣りのシーズン到来」とそれまでのスキーをしまって釣り竿を出す楽しみもあり、また春になれば「それなりにガンバッテ働たらこう」というけなげ(?)な心構えも徐々に出来てくる。 それが田んぼも土手も去年の秋の風景と同じである。 他人(ヒト)は雪が降らなかった分だけ「雪スカシがなくてお前にとって楽だっただろう」と言うけれど、逆に私は腰を痛めてしまった。どうも人間の体(私の体)はそれなりに働く様にできているみたいだ。冬の「雪スカシ」がつらくても春になればもうすっかり忘れられる様に、人間は肉体的苦痛(死と関わりないような)は時が経てば忘れられる様になっている(たぶん他の動物もそうだろう。ただし精神的な苦痛に関しては、まだそれほど進化していない)。 例年いよいよ冬かという時には、「冬来たりなば 春遠からじ」と、カラ元気を出し、この辺では冬の最中である立春(二月四日)になれば、「今日から春だ」と勝手に思い込む。そして「春は名のみ…」と続き、やがて名残り雪かと思える日を迎え、養魚場の周り中ガラクタをそのままにして(まだ雪の中)生きている若草だけが雪を押し退けて地上に現れてくる。そして、今年の冬も終わりかと少々感傷的になり、春を迎える。 やはり私の様な、同じ事のくり返しの日々の生活であっても、いやそうだからこそ、いつも何かこじ付け(これを機会に…)生きているような人間には「冬の終りが必要だ」。 何か言いたげに降り、そして消えゆくなごり雪 若草に あてもなく降る なごり雪 |
| 第三十回へ |