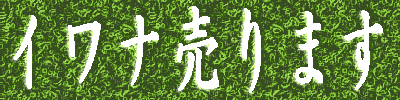 |
 |
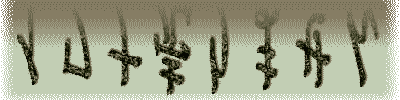 |
 |
| 河崎 徹 | |
| 河崎さんは、金沢近郊の医王山(いおうぜん)で、イワナやヤマメなどの養殖と、川魚料理の店「かわべ」をやっている、そろそろ落日の五十代。仕事より、魚釣りやら草野球やらにうつつを抜かし、店の方は、気が乗らないと勝手に閉めてしまうのが玉にキズ。(でも料理はウマイんだな)。いつもマイペース、ままよ気ままの行きあたりばったりエッセイからは、その人柄が伝わってきます。 |
|
| 第三十四回 「本が売れた(うそだろう)」 |
年明け早々龜鳴屋(勝井宅)を訪問した。勝井「正月から仕事がいそがしくて」、私「うそだろう」、と思ったが口には出さない。今の世の中、何が起きてもおかしくないと思っているから。 勝井「本が売れてその発送がいそがしくて」と、正月で少々ボケ気味の私の頭を必死に働かせて、どの本か、と思ってみるが、やはり「そんな訳ないだろう」。 売れて発送に忙しい本というのは、私の興味の薄い詩集だった。毎日十冊前後の注文がネットであり、「朝から大変だ」と文句を言っている。本が売れてはいそがしい、と文句を言い、売れなければやはり文句を言っている。「正月から本が売れたのだから、素直に喜べばいい」と私が言うと、横にいた奥さん「もっと言って」という顔をしている。ただ「お前(私)にだけはそんな事、言われたくない」という彼の気持ちもわかる(私も同じ「忙しいのがきらい」だから)。 ところでなぜ『詩集ないしょ』が急に売れるようになったのかとその理由を聞いたところ、フォーク歌手で詩人でもある早川義夫さんがネットのホームページでその詩集を紹介してくれ、それを読んだ人達が龜鳴屋へ注文してくれたという事である。 彼(早川義夫氏)が七〇年代、歌手でレコードを出してヒット作があるというので興味が湧き、さっそく娘と二人でカラオケ屋に行って、曲と人となりを探ってみた。 ところで「お前がカラオケ?」と言われそうだ。ずいぶん前、私はどこかの同人誌に「あんなもの(カラオケ)すぐ廃れるわ。私なんか、今まで人前で歌を唄うなんぞ考えた事もない。歌なんてものは一人風呂の中で唄うもの。金をもらってもやりたくない」と言っていた様だ。だが、私の娘がいろんな事に失敗して、元気のない時に娘の唯一の趣味であるカラオケに一緒に行き、その楽しそうな姿を見て、今の若者にとってカラオケ屋で歌を唄う事の意義が少しわかった様に思う。 私の大学生の頃、「君が代/国歌」に反対する教師からなぜ反対かを聞いた時、「自分達の青春時代(戦争中)は軍歌と君が代だけだった。それを聞くと、今でも心がジーンとなる。それは、当時のあの忌まわしい過去とセットになって身についてしまっているからだ。だからこそ封印しなければならない」と、歌とは人の心をコントロールする恐ろしい力がある事を知らされた様に思う。 今、思い起こせば、私達の青春時代(そんないいものではなかったが)、それは学生運動の時代と同時にフォークソングの時代でもあった。今はハゲ頭のオッサンになった吉田拓郎を久しぶりにテレビで見た。あの当時の彼はカッコよかった。その彼が自分の作詞作曲した「えりも岬/森進一/歌はうまいが性格がいまいち」が年末の一大イベント「レコード大賞」に輝いた時の光景を思い出した。当時「レコード大賞」と言えば紅白歌合戦と人気では双璧であり、既存の歌謡会最大のイベントだった。そこに新参者のフォーク歌手の吉田拓郎が出てきて何を言うのか興味があった。タキシード、ドレスの正装のみんなの前に大賞で最後に出てきた彼は、ジーパン姿で長髪でほとんど何もしゃべらずボーと立っていた。その時私は「これが彼にできる既存のものに対する精一杯の自己主張」かと思った。ただ今から思えば、集団でカッコのいい事を言っていた大学紛争がほとんど何も残さず消えていった事を思えば、三〇年以上経つこの年になってもノーテンキでその頃のいろんな歌を唄える私達にとってはありがたい事である。そうでなかったら、「君が代か女の操」ぐらいを唄って若者から顰蹙を買っていたかもしれない。 話が横道に外れてしまったが、結局彼(早川義夫氏)のヒット曲は「サルビアの花」とわかったが、聞いた事があった様な、ない様なで、演奏に合わせて「あ、とか、う、とか」言っているうちに歌は終ってしまった。 |
| 第三十三回へ |