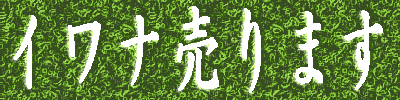 |
 |
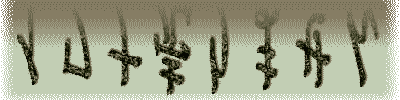 |
 |
| 河崎 徹 | |
| 河崎さんは、金沢近郊の医王山(いおうぜん)で、イワナやヤマメなどの養殖と、川魚料理の店「かわべ」をやっている、そろそろ落日の五十代。仕事より、魚釣りやら草野球やらにうつつを抜かし、店の方は、気が乗らないと勝手に閉めてしまうのが玉にキズ。(でも料理はウマイんだな)。いつもマイペース、ままよ気ままの行きあたりばったりエッセイからは、その人柄が伝わってきます。 |
|
| 第三十七回 「ドボンいやガボン」 |
この頃私の友人のMさんは体調がよさそうだ。「酒をやめた」いや、「タバコをやめた」いやちがう、「いい仕事が入った」いや、それもちがう(私と同様仕事がいそがしくなると体調が悪くなる)。 実は彼の下の娘さんが、ドボン、いやガボンから二年ぶりに帰ってきたからだ。ただ「十二月には帰る」と聞いたこのオヤジは、十二月一日にでも帰ると思ったらしく、今日か明日かと待っていた。一方彼女の方は、あちこちフランスなぞへ寄り道して十二月中に帰るつもりだったらしく、本当に帰ってきたのは年も押し詰まってからだった。それでも彼から「やっと帰ってきた」という連絡を受けた時は、ようやく安心したという様子だった。 初めて、彼女が「ガボンへ行く」と聞いた時、私の周囲の人間達はみな「ガボンてどこや?」という具合だった。さっそく我が家の地球儀で調べてみると、アフリカのほぼ赤道直下で太平洋に面した国(旧フランス領)である。彼女は、青年海外協力隊の一員として、二年間当地で働くという事であった。 彼女が決心したその後で、お父さん(Mさん)以外の人にはもう了承を取ってあるけれど、「問題はあのお父さんや」と、私に打ち明けた。アフリカ、なるほど私自身が行くのだったら「野生の王国、四大文明の発祥地、リビングストンのアフリカ探検」と心おどるだろう。しかし、もし私の娘が一人でそこへ行くと言ったら、「暗黒大陸、奴隷の発祥地、独裁者アミン」と心配な事ばかり考えてしまう。だから、この話を聞かされた時のMさんの気持ちもわかる。私がどうこう言える立場ではあるまい。ここは親子で解決するしかないだろう、と思っていた。 それからしばらくして娘さんに会ったら、彼女「ウチのお父さん、バカや」、私「どうした?」、彼女「お父さんに話したら、急にポケットから財布(全財産)を取り出して『これでどうにかならんか』(考えを変えないか)」と言ったという。思わず私も笑ってしまったが、どこかMさんの気持ちがわかるような気がした。彼女はお父さんに似て、「ものおじしない」性格で、「女にしておくのはもったいない(女性に対する差別用語)」タイプの人間である(ただし、お父さんと異って酒乱の気はない)。それ故、アフリカであろうが、ベトナム(彼女はよく仕事でベトナムの奥地へ行っていた)であろうが、心配はないだろう、と周囲の人達は言っていた。彼女にすれば、若くてしたいことができる時にいろんな体験をしたい、という思いだったのだろう。 私にも、若い頃にはいろんな所へ行ってみたい、という願望があった(特にいやな事があった場合には)。人は、その願望によって生息範囲を広めていった様に思う。たぶん私の先祖は何万年か前、モンゴルか、その辺の狩猟民族で、それらに特有の「どこか未知の場所に行けばもっといい事があるのでは」という思いで、あちこち獲物を追ってウロウロしている内に、日本にたどり着いたのだろう(いつもの私の大胆な発想)。例えば釣りでいうと、私が地元金沢港であまり釣れない時に県外まで出かけて行って、そこの釣り人に「ここは釣れますか?」と聞くと、そこの釣り人は「金沢港へ行け、あそこは釣れるそうな」という事がよくあった。それでも今も私は、未知の釣り場はよく釣れそうだと思っている。釣りの話だけではなく、今、思い起こせば「未知の場所へのあこがれて」失敗(?)した事は山ほどある。 高校生の時、私の通っていた学校は、当時の国鉄(今のJR)金沢駅からのバス通学であった。そのバスは、金沢から富山を通り抜け、七、八時間かけて岐阜の「美濃白鳥」が終点だった。その美濃白鳥は霊峰白山の裏側にあたり、一度は行ってみたいと思っていた。純白の白山の向こうにある「美濃白鳥」は、何と美しいヒビキの地名ではないか。詩人のカールブッセの「山のあなたの空遠く、幸いすむと人の言う…」。ある日(いやいや学校へ通っていた日)、思い切って高校前で降りず、そのまま「美濃白鳥」まで行ってしまった。今思い出そうとしても、そこがどんな町(村)だったのかさっぱり覚えていない。それが、学校をさぼったのがバレて、職員室でしかられた事は覚えている。小心者の私が学校をさぼって行ったのだから、よっぽど行きたかったのだろうけど。 その高校生活も終わりに近づき、勉強ぎらいだけど働く気もなかった私、そんな時、一冊の受験用雑誌を見ていたら、「これだ」というのがあった。水産学部(何科だったか覚えていない)で四年終了後、一年かけて世界一周、遠洋航海、というのがあった。進路指導の「お前に入れるような大学はない」というはげまし(?)もあって、一浪して世界一周を目指す事にした。ただ浪人中、水産関係の仕事をしている兄の計らいで数日間漁船に乗せてもらい、その時に散々船酔いに苦しめられた。又、中学生時代に同級であった現役の船乗り(タンカー)から、船酔いに弱く酒に弱い(今でもアルコールは苦手)奴は「船に乗ると苦労するぞ(航海は酒だけが楽しみとの事)」と言われ、北海道と鹿児島を受験したものの、結局地元におさまってしまった。それでも、地元の大学へ入ってから、毎年のように与論島や西表へ行っていた。「南国はいい。むずかしい事を考えられなくなる」と、暑くなると海へ潜って遊んでいた。一時「ここで暮らそうか」と思った事もあった。だが、何度か行くうちに、そこで生活している人の姿を見れば、やはりそこで生活していくのは私にとってそんななまやさしい事ではないと知らされ、またしても挫折してしまった。南がだめなら北はどうか、と八年間いた大学を卒業して、北海道へ向かった。秋から冬への北海道、しかも人里離れた山の中の養魚場での三ヵ月間ほどの生活(ほとんど私一人の生活)、結論から言えば、やはり遊びに行くにはいい所だけれど、北の宿で寒さこらえて仕事するのはきつかった(もっとも寒さだけでなく、北海道で理想の養殖の考え方がまったく相手にされなかったという事もあって)。それで何の未練もなく、北海道から引き上げてきた。 このように、私の若い頃の「未知の土地へのあこがれ」は散々なものだった。 彼女は私とちがって、もっと地に足の着いたものだろうけど。 ところで、ガボンで二年間生活してきた彼女に対し、「ガボンの人ってどんな感じ?」と聞いたら、彼女曰く「仕事をしない事に罪悪感がないみたい」と、私「急に親近感が湧いてきた。一度行ってみたいドボン、いやガボンへ」 |
| 第三十六回へ |