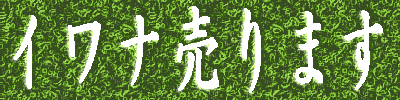 |
 |
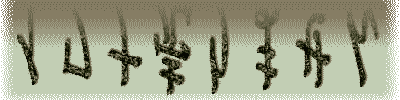 |
 |
| 河崎 徹 | |
| 河崎さんは、金沢近郊の医王山(いおうぜん)で、イワナやヤマメなどの養殖と、川魚料理の店「かわべ」をやっている、そろそろ落日間際の六十代。仕事より、魚釣りやら草野球やらにうつつを抜かし、店の方は、気が乗らないと勝手に閉めてしまうのが玉にキズ。(でも料理はウマイんだな)。いつもマイペース、ままよ気ままの行きあたりばったりエッセイからは、その人柄が伝わってきます。 |
|
| 第四十一回 「小劍コラム集雑感、あるいは消えた(一一一)の事」 |
かなり以前の事だが、亀鳴屋で戦時中、芥川賞候補になった事もある伊藤人誉氏の少々ミステリアスな小説『幻の猫』を出版する事になった。伊藤さんの原稿と同時に写真(顔)が送られて来た。伊藤さんはもう高齢であり、それ相応の「お顔」とみた。だが、彼(勝井)には「この写真はどうも」と不満気だった。私は、「じい様の顔を今さらいじくっても仕方ないだろう(失礼)」と思っていた。 それから数日後、彼(勝井)は写真家の小幡君を伴って伊藤さん宅(埼玉)まで出かけて行って写真を撮った(資金もないのに)。その写真を見せてもらって「なるほど、『幻の猫』を書いた作者の顔で、どこか不思議な力を感じさせる」ものになっていた(写真家の小幡君の腕もあるだろう)。 さて今回の『上司小剣コラム集』、ここでも最初のページをめくると、彼(小剣)の写真が載っていた。見た瞬間、「これは中々むずかしい(?)人物かも」と思った。これまでも亀鳴屋出版の本には今回の『上司小剣コラム集』や『藤澤清造貧困小説集(この男だったら公園で野垂れ死にしそう)』等々、いずれの本にも一枚の写真で作者の人物像を浮かび上がらせる工夫がみられる。亀鳴屋の造る本は、メジャーにならなかった作家(私が知らないだけか)の文章を独自の視点で浮かび上がらせ、それに写真を添え、工夫(こだわり)とたっぷりと時間をかけ製本していく(ムダが多いと一部の人(私)は言う)、そこに弱小出版社の存在意義があるのだろう。(たまに亀鳴屋の事をほめておけば、後で何かいい事があるだろう(前回は香典返しのビール券だった))。 さて、今回の上司小剣だが、写真の通りやはり一筋縄ではいかない人間のようだ。彼(勝井)の家で本を買った日、彼曰く「話が沢山(一話から八五二)あるので一話から順に読んでいたら大変だから、適当な所を開いては読む方がいいだろう。それに中には小学生の書いた様な文章(?)もある」との事。私が本を読むのは今では寝床の中だけ。しかも、その寝床に入ったら三〇分以上起きてはいられない。長い話だと、次の日どこまで読んだかわからない。そんな私(年寄り)には短い話が沢山ある方がありがたい。適当な所を開いて、短い話を何話か読んで眠りに着ける、ただそれでも問題がおきる。人間は(私だけかも)どうも適当な所を開く、というと不思議と同じ所を開いてしまう。そして、同じ所を読んでしまってから「前に読んだ様な気がする」となる。「困ったものである」。 年寄りのグチはそれくらいにして、本題に入ろう。 勝井の言う様に「こんなの小学生でも書ける文章(失礼)」と思うもの(一話)、中々奥の深そうな事を言っている様だが、私にはそれがわからないというものも沢山ある。又、あの時代(明治、大正)に作者が言っている事が今の時代にピッタリというものもある(一六〇話等)。やはり半眠りの状態で読んでいては、中々わかりにくい人物の様だ。それでも読んでいくうちに、自分がわからないのは、彼が新聞社という組織の人間(コラムニスト)であるからではないだろうかと思うようになった。私の様に自由、気ままに書けない(書いてはいけない)という事を加味すれば、なんとなくわかる様な気がする。その日の新聞内容とのバランス(例えば青少年の犯罪が大きな記事になれば一話の様なコラムになるかもしれないし、)あるいは、その時代(明治、大正)の風潮を意識して書いた(書かざるを得なかった)ものもあっただろう。特に本の後半部(金魚のうろこ−大正時代)では、奥歯にものがはさまった様な言い方が目立ち、七六九、八二二話あたりでは、いささかストレートに物が言えないグチ(いらだたしさ)が感じられる。この辺の話を読みながら、彼の写真を見ると、なんとなく、彼の人物像がわかる様な気がする。(できればその年代(明治、大正)の出来事(新聞記事)でも、何回かに分けて載せてくれればそれぞれ話がより解りやすく、又文章に深みがあったかも(亀鳴屋にそんな予算はないが))。 さて、ここまで書いて、彼(勝井)の家へ行ったら、今回はめずらしく順調に本が売れているとの事。それで、もうここで書く(無責任に批評する)のをやめた。「お前の文章でせっかく売れていた本が売れなくなった。お前のせいや」といわれたら困るから。 消えた番号(年金の話ではない) その時(彼(勝井)の家へ行った時)、彼はひどく落ち込んでいた。原因は一から八五二話まであるはずの話が、一一〇話の次が一一二話となり、一一一話が抜けてしまっていたという事だった(私の想像では、一一〇番(警察)を見て動揺して一一一番を飛ばしてしまったものと思われる。[龜鳴屋注 底本とした『小劍随筆その日その日』自体、通し番号の一一一がとんでおり、これに気付かぬまま一一一があるものと思っていたという大ポカ、そりゃへこみます。ですから実際の収録数は八五一篇])。 ちなみに抜けた一一一話を、前後(一一〇と一一二)のつながりから、私が勝手に話を造ってみた。 一一一 人間の歴史は、人間の動物性と理性とかいうものの攻めぎ合の結果である。この状態はあと数万年、いや数十万年(その間に人類は亡びるかも)続くだろう。その攻めぎ合に割って入るのが哲学である。時代に合った哲学が必要だが、今はそれがない。 ところで、私も彼の奥さんも、彼をなぐさめるつもりで、「話の内容ではないので、「それくらいは」と言ってはみたが、「本造りの人間としては、それはゆるされない事」、さらに「何度も何度も読み返し、まちがえのないよう気をつけてきたのに」とグチる事しきりで、私のなぐさめも効果はなかった。彼の家を出て、ふと思うところがあった。「確かにまちがいはよくないし、完璧を期すのもいいだろう。だとすれば、己(勝井のまちがいだらけの人生設計)をこの際なんとかしろ。(奥さんのためにも)」(これでビール券はなくなったな)。 追伸 他人様の文章を全部読んだかどうかもわからないのに批評し(それも中途半端)たのには、少々気が引ける。文章を書く人に、わずか一行に、又一行にその人の本音、本心「言わんとする事」が書かれている場合がある。(今回の私の場合も) |
| 第四十回へ |