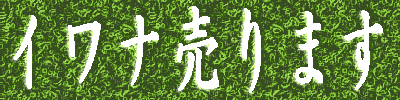 |
 |
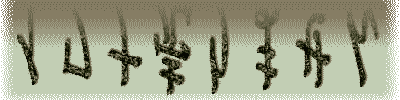 |
 |
| 河崎 徹 | |
| 河崎さんは、金沢近郊の医王山(いおうぜん)で、イワナやヤマメなどの養殖と、川魚料理の店「かわべ」をやっている、そろそろ落日間際の六十代。仕事より、魚釣りやら草野球やらにうつつを抜かし、店の方は、気が乗らないと勝手に閉めてしまうのが玉にキズ。(でも料理はウマイんだな)。いつもマイペース、ままよ気ままの行きあたりばったりエッセイからは、その人柄が伝わってきます。 |
|
| 第四十三回 「妄想(秋の一日)」 |
「自然がいっぱいの風景も毎日見ていると飽きてくる」 ここに住む村人は言う。確かに私もその様に思う。だが、それでもフト「ああ、イイ風景だなあ」と思う事がある。 それが短いがこの秋だ。ぼんやり外をながめながら、文章でも書こう、いや書けなくてもいい、くずれかけたボロ小屋(私の仕事場)に住んでいようが、やらなくてはいけない仕事が山ほどあっても、どこか記憶のかなたに押しやってくれるのがこの風景だ。そんなことを思っていると植木屋さん(Mさん)がやってきた。 「いい日だな」、私「いい日旅立ち(山口百恵の歌)」、Mさん「どこへ旅立つ」、二人しばらく沈黙。私「どこへ行くかわからぬが行き着く先はホームレスやな」、又沈黙。Mさん「晴耕雨読というが、わしらの場合、晴休雨休やな」、私「だいたい、わしらみたいな、おってもおらんでもいい様な年寄りが読む様な本が今はない、今さらがんばって新しい知識を身につけてどうする、人間、年を取ると子供に返るというから、童話でも読もうか、童話というのは空想の世界で、今のわしらの勘違いの世界観、妄想の世界に通じるものがある」、Mさん「それって、ボケの始まり?」と、どうも年寄り二人の話しはグチっぽくていけない。 そこへ我家の娘(長女)がやって来た。 もう三十才を過ぎたがまだ就職ができていない、それで今回も落ち込んでいるので、彼女にとっては最も苦手な肉体労働である私の仕事の手伝いにやって来た。彼女の場合、いつも就職しようとすると不思議と世の中不景気になる。就職なんて「運のもの」と思っている私からみれば、運の悪い子である。それに世の中の流れに乗れなかった(私も同じ)事もある。「それがどうした。父さんの家系は先祖代々神職であり、何がなんでもアクセク働く様な血筋ではない(説得力はない)」と言えば、「それは父さんの生き方でしょう(“バカな生き方”と言わない所が心のやさしい子である)」と言われてしまう。この私から見れば、今の世の中の流れに、ちょっと乗りおくれただけで横にはじきとばされ、それによって傷ついた傷口にみんなで塩をぬる様な社会である。「私もその一人だったかも」「父さんはもう六〇年も生きてきたからいいけど、私はこの先どう生きていけばいいの」とかなり深刻である。「おもしろき事もなき世をおもしろく」、私にすれば私の様にカラ元気でもいいから、毎日を楽しそうに生活してほしいものである。たぶん彼女は「そんなの無理」と言うだろう。 「肉体労働は生物が生きていく基本だ」と言っている手前、娘が手伝いに来た以上はMさんとのバカ話しはやめて、「さあ、働くぞ」と自分にも言い聞かせて仕事を始める。 鼻先きへ 仕事が何ぼのものじゃと 赤とんぼ いつもの様に最低限の仕事を終え、娘も帰り、私の与えるエサの分だけ忠義をつくす二匹の犬との散歩に出る。紅葉した木々に夕日があたり、えも言われぬ風景である。 今日の日も わすれるがごときに 秋の夕暮れ |
| 第四十二回へ |