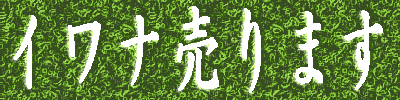 |
 |
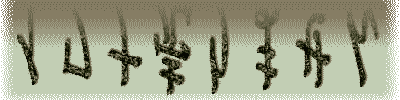 |
 |
| 河崎 徹 | |
| 河崎さんは、金沢近郊の医王山(いおうぜん)で、イワナやヤマメなどの養殖と、川魚料理の店「かわべ」をやっている、そろそろ落日間際の六十代。仕事より、魚釣りやら草野球やらにうつつを抜かし、店の方は、気が乗らないと勝手に閉めてしまうのが玉にキズ。(でも料理はウマイんだな)。いつもマイペース、ままよ気ままの行きあたりばったりエッセイからは、その人柄が伝わってきます。 |
|
| 第四十六回 「「したむきな人々」が造った本」 |
「ひたむきな人々」に続いて「したむきな人々」という他の本屋からはまず出版されない様な画期的(しょぼくれた)題名の本が龜鳴屋から出た。 「ひたむきな人々」だったら釣れても、釣れなくても、周囲の冷たいし視線にももめげず、この齢まで延々と釣り続けてきた私みたいな人の事を言うのだろう。ただし、その事が何か社会的評価を受けた場合(例えば今頃はやりの感動するお話とか)であれば小説のネタになるだろう。しかし、私の場合の様に三十年以上、釣りも含め今の仕事をやってきた事に「どれだけの意味があったのか」とゴチャゴチャ考えても、又(よくもまあ三十年も)と少々の「お褒めの言葉をいただいた」としても、それが「ひたむき」と言えるのか、と考えれば自ずと「したむき」になってしまう。 この本のいくつかの話の中にも、「ひとむきな時もあった」「ひたむきになりたい」でも結果として「したむきになった」「したむきにならざるを得なかった」ごく一般的な人々の話であり、どこか私の人生にもあてはまる様で読んでる途中でホロッとさせられる事もあったが、他の本のように読んだ後の「感動」なるものとは縁がなかった。 さて、私の勝手な「ひたむき、したむき」論はこれくらいにして、いつもの様にエラソウな「本の批評」をやってみたい。 まず龜鳴屋店主好みの独特の雰囲気がある本の表紙、いかにも「したむきな人々」を連想させる表紙だけれど、まともな(?)人は「なに、この暗い表紙、こんな本読みたくない」となるだろう。そこが彼(店主)のねらいだろうが、いかんせん、これでは今回も五百部売れるか心配である(その結果、彼はまた「したむき」になるだろう。) 私はめったに本は買わないが、買った本は、まず「まえおき」「あとがき」を読む事にしている。今回も「まえおき」「あとがき」から読ませてもらった。そこには、実に「ひたむきな人々」「したむきな人々」に対する解説がすばらしく書かれていた。これはきっと、彼らの文章力もさることながら、本人達の自分の置かれている境遇が「したむきな人々」とぴったり一致したからではないだろうか。この「まえおき」「あとがき」を読んだら、もう本文は読まなくてもいい様に思えてきた。案の定、読んだ本の内容は予想通り「まえおき」「あとがき」にすべて言い尽くされており、エラソウに批評と言ってはみたものの、私の様な素人の出る幕ではなかった様だ。 ならば、せめて最後に私の「独断と偏見」でもって私を含めて「したむきな人々」の存在意義(少々オーバー)を考えてみたい。 「日本という国を支え続けたのは「したむきな人々」である」 今は亡き、作家城山三郎、彼の青春時代、日本は戦争をしていた。彼はひたすら軍人になる事をめざし生きて来た。その彼が敗戦の報を聞いて地面に泣き伏し、ようやく我に返って顔を上げて空を見た時、そこにあった青空に、「こんなにきれいな空があったのか」と感激したと同時に、今までずっと「したむき」で生きてきた自分に気づいた、と言っている。作家城山だけでない、戦争体験者の多くが「したむきな人生」だったと語っている。何もこの戦争時だけが「したむき」だったという訳ではない。二百六十年も安定が続いたと言われる江戸時代でも、身分制度で一番上の殿様だけがふんぞり返り、下の者(町人、農民)は上の人達の前では、ひたすら「したむきの人々」であった。実際には、その町人、農民がその社会(くらし)を支えていた。今の世の中だって、身分制度とは言えないが格差社会である。あるエラソウな大臣が「国は国民一人一人の努力で成り立っている」と言っているが、それは口先だけの話で、会社社会でも同じである。いつも上から押さえつけられ、追い立てられている「したむきな人々」、それでもなんとかやっている(生きている)「したむきな人々」。ひょっとして、これこそが「ひたむきな人々」なのでは、と思えてきた。 龜鳴屋次回作は、「したたかな人々」、次々回作は「しぶとい人々」に決定しました(勝手に決めるな)。 龜鳴屋の店主から、「何か書け、さあ書け、早く書け」と脅迫され、ひたすら「したむき」状態で、やっと書けてホッと一息ついて空を見上げたら、いつの間にか秋の気配に変わっていた。 ホッとして 見上げる空の 高さかな どこへ行く どこまで行くのか 赤トンボ |
| 第四十五回へ |