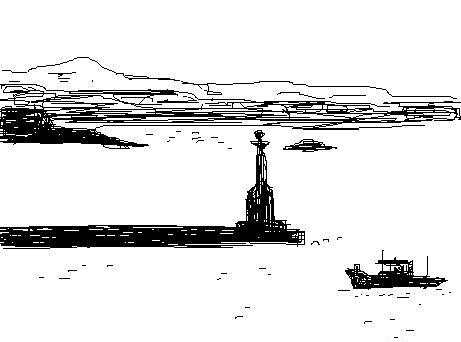 |
 |
| 佐藤 敬太 |
| 第2回 さよならの轍 アッキちゃんの白いジープ |
||
| 幼いころ、僕は叔父が好きだった。叔父は父の弟で、名前は昭和といい、親類や親しい人たちからはアッキと呼ばれていた。 その当時、叔父は山形に住んでいた。叔父は小さな土建屋の社長をしていて、一年に何度か、僕の家でもある岩手県の実家までやってきた。盆や正月といった時期には、たいてい叔母や従姉妹の祥子ちゃんも一緒だったけれど、仕事が途切れたときなどを見はからって、ふらりと一人でやってくることも多かった。 叔父はいつでも両手いっぱいの土産袋とともに現れた。大きなアワビの殻に隙間無く詰められた蒸しうにや、山形特産の佐藤錦というサクランボ、それから白い包装紙で一把ずつ包まれた高級そうな蕎麦など、我が家の食卓では滅多にお目にかかれない逸品ばかりだったので、叔父がやってくると、その日の夕食はいつになく華やぐのだった。 祖母や父の話しによると、子供のころの叔父は手のつけられない悪童だったらしい。そのころの面影は、いい大人になったあとも気性の激しさとなって色濃く残されていた。それまでにこにこと笑っていたかと思うと、突然ささいな一言に腹をたて、周囲もはばからず怒鳴り散らすこともあり、叔父のそうした一面は、子供だった僕の目にずいぶんと恐ろしげに映った。気の小さい僕などは、叔父を前にするとおどおどしてしまい、思っていることの半分も口にすることができなかった。遠い昔の子供心をありていに説明するのは難しいのだけれど、叔父のことを想うとき、畏怖と思慕という二つの相反する感情が、僕の中でいつもせめぎあっていたような気がする。 遺伝によるものなのか、それとも長年の生活習慣によるたま物なのか、一族の大人たちはみな酒が強かった。そして、いつも楽しそうに飲んだ。親戚が集まると、夜は決まって飲めや歌えやの宴会となった。酒宴の主はたいてい叔父で、どこか腫れぼったい感じのする大きな顔を真っ赤に染めながら、声をはりあげて冗談などを云い、場を盛り上げた。やがて調子づいてくると、叔父は決まってずんぐりとした体を大儀そうにテーブルの外に投げ出し、ズボンのポケットから札入れをとりだすのだった。抜き取った何枚かをこれ見よがしにひらめかせ「うめぐ歌った奴には金やるぞ」と、子供たちをけしかけた。そんな言葉に踊らされて、真っ先に名乗りをあげるのはちゃっかり者の姉で、十八番のキャンディーズを振り付け混じりに披露しては、しっかりと千円札を手中におさめた。 そのころ僕は、父や祖母と一緒に詩吟を習っていた。自分で歌うのが苦手な叔父は、実家を訪れるたびに父に詩吟をせがんだ。父は元来生真面目な性分で、叔父のような遊び心を持ち合わせてはおらず、先生とまで呼ばれるその歌声を余興で披露することなど滅多になかった。それでも、弟のじきじきの懇願には特別な効力があるのか、「いやあ」などとさんざんもったいぶったあげくに、最後はいかにも渋々といった感じで席を立つのだった。安普請の天井に父の詩吟が反響すると、叔父はじっとうつむいたまま聞き入り、やがて心から感心したように「やっぱりあんやはんめなあ」とため息をもらした。叔父の口から漏れる「あんや」という響きは、土地の言葉が持つ独特のやわらかさがあって、周囲の者たちをほのぼのとしたやさしい気持ちにさせた。 先生の出番が終わると、叔父は必ず僕の方に向き直り「今度は敬太だ」と云った。本当のことを云えば、難しい漢詩ばかりで節回しも単調な詩吟というものに、僕はそれほど面白みを感じているわけではなかった。それどころか、李白や菅原道真といった偉人たちが書き残した詩を、自分の人生になぞらえて熱唱したがる大人たちの世界を、いくらか興ざめた思いで見ていたのだった。詩の意味などほとんど理解できないにもかかわらず、民謡の持つ艶と明るさが詩吟にはないな、などとまったく生意気なことを感じていたのだ。僕が教室に通うことを、父は何よりも楽しみにしていた。父を失望させないために、仕方なく詩吟を続けていたと云ってもよかった。 そんなわけで、酒が入るとやたら詩吟を聞きたがる叔父の性癖は、僕にとっては迷惑この上ないものだった。叔父の言葉で座はおおいに盛り上がり、大人たちが期待のこもった目をいっせいにこちらに向けるので、僕はますますげんなりとした気分になるのだった。「やんだ、うだわね」 そう云ってそっぽを向くことができたなら、どんなに晴れ晴れとした気持ちになったことだろう。しかしあのころの僕にとって、叔父の言葉は絶対であった。叔父の望みをむげに拒否する勇気など、とうてい持ち合わせてはいなかった。父の場合とは違って、僕は本当に渋々と席を立った。子供が小難しい詩吟を詠うことで酒宴はますます盛り、僕は誰よりもたくさんのお金を手に入れた。僕にとって「子供のど自慢」は、姉や従姉妹たちのように自らが楽しむものではなく、ていのいい小遣いかせぎの場でしかなかった。 ある晩の宴会で、僕は一度だけ周囲の期待を裏切ることを決意した。大人たちの機嫌をおもんぱかって、如才なく立ち振る舞ってきた僕にとって、それは大きな冒険とも云えるものだった。テレビで覚えた「宇宙戦艦ヤマト」を高らかと歌うときの僕は、きっといつにも増して活き活きとした顔をしていたことだろう。途中、一番と二番の歌詞を取り違えてしまったのは大失敗だったけれど、大人たちがそれに気づいていたとは思えなかった。少なくとも、そのできが姉の歌うジュディオングに負けていたとは思えない。けれど、始終憮然としたまま腕を組み、歌い終わっても拍手すらしようとしない叔父を見たとき、僕はすぐさま自分のあやまちに気がついた。 「いまのは50点だな」 怒気すら含んだ冷たい声でそう云うと、叔父は僕の目の前で千円札をびりびりと引き裂 いた。叔母が慌ててたしなめても意に介さず、震えながら紙幣の半分を受け取った僕に、叔父はこう云い放った。 「なんだ、この程度のことで顔色を変えるのか、敬太もたいした男にはなれねえな」 叔父の破天荒なふるまいは、ときにするどい切尖となって幼い心を傷つけた。それでも僕は、叔父を憎むということができなかった。凡庸な父にくらべると、不確かではあるけれど、どこか抗しがたい膂力(りょりょく)のような魅力が叔父にはあった。それは理性を超えた衝動となって僕の心をからめとっていた。 当時、叔父は三台の車を持っていた。幌付きの白いジープと真赤なRX−7、それから名前のわからないセダンの高級車、どれも田舎ではあまり目にしない洗練された車ばかりで、そうした高価な車を、その日の気分によって乗り分けているようだった。三台の中で、僕は白いジープをとりわけ気に入っていた。他の二台に比べると少々乗り心地は悪く、冬はドアの隙間から冷たい風が吹き込んだけれど、どんな悪路でもがんがん突き進んでゆく力強さが、とても頼もしく思えた。 我が家にも一台だけ車があった。製材所で働く父が会社から支給されたバンで、くすんだ白いボディーには、青いペンキで社名が書かれていた。エンジ色のシートは乾パンのように硬く、後部座席に乗るときはいつも背中を直立させていなければならなかった。窓の開閉はもちろん手動である。そんなおんぼろ車でも、家族の思い出が沢山つまっていることに変わりはなく、僕はそれなりの愛着を感じていた。けれど叔父が山形からやってきて、車庫に二台の車が並んだとたん、僕は父の車を正視するのが恥ずかしくなるのだった。あや彩やかな光沢に包まれた山形ナンバーの車のかげで、ところどころペンキの剥げかけた「小林林産」の文字は、あまりにみすぼらしかった。みんなでどこかへ出かけようかなどと話しがまとまると、僕は真っ先に玄関を飛び出して叔父の車に乗り込んだ。やわらかいシートに深々と沈みこみ、鼻先をただよう柑橘系の芳香剤にうっとりしながら、つかの間有頂天になった。やがて、やや遅れて家から出てきた父や母が、微笑みながらバンのドアを開けると、僕はたちまち良心の呵責にさいなまれ、胸がふさがれるのだった。父や母がどう感じていたかはわからないけれど、その瞬間、僕は間違いなく家族の裏切り者だった。 ある日、叔父は僕を散歩に誘った。家から徒歩で20分ほどのところにある、羽黒山という小さな山まで、二人で歩いた。山道の入り口にある大きな鳥居を抜けると、そこからは急峻な砂利道が杉林を縫うように続いている。山頂の神社へと続く石段までくると、叔父は息を切らしながら云った。 「このあだり一帯はな、昔『蝦夷』と呼ばれていだんだ。都の人だぢはここに住む者を野蛮な人間だど思ってだみでだげど、それでもみんなで仲良く暮らしてだんだ。それがよ、ある日、この土地を奪うべどして、兵隊がいっぺやって来たのさ。そのどぎここを守った蝦夷の大将がな、アテルイという英雄だ。北上川とこの山を砦にしてよ、アテルイは頑張ったんだ。そりゃあ、つえがったんだ」 叔父は、まるでその目で見てきたかのように、はるか昔の戦について語り始めた。 「それで、どうなったの?」 「最後があ?アテルイは頑張ったんだげどな、都から来た征夷大将軍の坂上田村麻呂というのがこれまたつえくてな、向ごうは兵の数もずっと多がったし、とうとう負げて殺されてしまったのよ」 田園と山なみを見晴るかすかぎりの辺鄙でのどかなこの土地が、歴史の中に亡者たちの血で塗りたくられた一頁をはらんでたなどとは、にわかには信じがたいことだった。そして、平和だったこの土地を、天下泰平という大儀のもとに蹂躙していった、セイイタイショウグンのサカノウエノタムラマロという男が、なんだか無性に憎らしく思えた。 「ほら、この石段の脇を見ろ。大きく窪んでるべ?俺が子供のころはよ、まだここに水が張ってあったんだ。実はな、敗れた蝦夷の兵士たちが、ここに鎧や刀、財宝なんかを埋めたっていう伝説があるんだ。不思議なごどに池の水はいつも真っ赤な色をしててな、それは兵士たちの血を吸ったがらだど年寄り連中は云ってだな」 「それじゃここを掘ったら宝が出てくるの?」 堆(うずたか)った泥の下から黄金色に輝く財宝が掘り起こされるさまを思い浮かべ、僕の胸は大きく高鳴った。 「ああそりゃあるさあ。でもな、だいぶ昔の話だがらなあ、いっぺえ掘らねど出でこねべなあ。それにな、ここを掘るど血の雨が降るっていう言い伝えもあるんだ。だがら恐ろしがって誰も掘らねのさ。」 あたりには一抱えもある杉の木が所狭しと屹立し、空は天蓋を閉ざしたように常緑の葉むらでさえぎられている。降りしきるのはかすまびしい蝉の声ばかりで、陽射しはほとんど入らない。叔父の言葉はまことしやかな響きとなって、ほの暗い社の森に溶けいった。 叔父の趣味は魚釣りで、そうした一面も僕にとっては魅力の一つだった。一口に釣りと云っても、狙う魚の種類や、仕掛け、釣具の選択など、人によってさまざまな好みがある。上級者になればなるほど、より細分化された世界にのめり込んでゆくのが釣りの世界では常套だった。叔父の場合は、とりわけ渓流釣りを好んだ。山道を走っている途中、雰囲気のよい川に出くわすと、必ずといっていいほど路肩に車をとめ、川原に降り立って魚のいそうな瀬や淵に視線を走らせた。 「僕も釣りをしてみたいな」 ある日そう打ち明けると、叔父はあけすけな笑みを見せながら「敬太に釣れる魚がいるかな」と云った。それでも、すぐさま僕を連れて町の釣具店に行き、惜しげもなくグラスファイバーの延竿を買い与えてくれた。初めは近くの池でフナ釣りを教わり、次にやってきたときは川の瀬で毛ばり釣りを習った。上流に対して斜め45度の角度に体を向け、頭の上で円を描くように竿を振ってできるだけ川上へと仕掛けを振り込む。少しずつ下へと流されてゆく仕掛けの位置を、三角錐の浮で確認し、仕掛けがめいいっぱい下流まで流れたら、再び竿を振って仕掛けを上流に飛ばす。これが叔父に叩き込まれた毛ばり釣りだった。 「昼間はまるで話にならねんだ」 経験から得られた叔父の言葉に嘘は無かった。コツコツという振動が、グラスファイバーの竿を通して手のひらに伝わってきたのは、西日が川面を照らし始めたころだった。慌てて竿をあげようとする僕を制し、叔父は「まだだ」と云った。再びあたりがあって、穂先がぐんとしなった。叔父はそれでも表情を変えない。さらに大きな力が竿先に弧を描かせたところで、叔父は初めて「あげてみろ」と云った。虹のように美しい斑紋をにじませたオイカワが三匹、銀色の体をひるがえしながら胸元に飛び込んできた。 「すごい!一度に三匹だよ」 僕が歓声をあげると、叔父は当然だと云わんばかりに大きくうなずいてみせた。仕掛けには、毛ばりは五本つけてあり、叔父は三匹目の魚が食いついたのを確認したあとで、僕に竿をあげろと云ったのだ。 叔父が初めて渓流釣りに連れて行ってくれたのは、小学校の高学年のころだった。秋田県との県境に連なる奥羽山脈のふもとの川に車は向かった。川面に膝までつかって竿を振る叔父を、僕は少し離れた木陰から見守っていた。その日は良型のヤマメが入れ食いで、叔父の腰にぶら下がった魚篭は、たちまち魚で埋まっていった。初めて渓流を訪れた素人の目にも、尋常ではない幸運が釣り人を取り巻いていることを感じさせた。いつになく興奮した面持ちで存分に釣りを楽しんだ後、叔父は僕に目配せをしてこっちに来るようにと合図を送ってきた。僕はこころもち頭を下げ、なるべく水しぶきを飛ばさぬよう、そろりそろりと叔父のもとへ向かった。僕を招き寄せると、叔父はようやく聞き取れるほどの小さな声と身振り手振りを使って、仕掛けの振り込む場所を指し示した。叔父の指示に従って、僕は竿を振った。ヤマブキの芯をくり貫いて作った目印が、せわしなく上下しながら徐々に下流に流されてゆく。途中、目印がふいに動きを止めた。それは単に、流れの複雑な作用によるものだろうと、僕は信じて疑わなかった。けれど、下流まで仕掛けを流し、竿をあげようとしたとたん、水の抵抗とは明らかに異なる強烈な手ごたえが、竿を大きくしならせた。魚が餌に食いついたのを、僕はうっかり見逃していたのだ。驚きは、すぐさま緊迫感をともなった喜びに変わった。懸命に竿を操って、苦労しながらなんとか足元まで魚を寄せた。道糸をたぐり、いとおしむように両手で魚を包みこむと、魚は観念したようにぐったりと手のひらに体を横たえた。かすかにあえぐ鰓からは血がにじみ出ていて、それは水面に一瞬不規則な帯をなし、すぐに清冽な流れの中にまぎれていった。朱の斑紋を浮き上がらせた錆色の体は流麗そのもので、澄んだ冷たい水に棲む魚がこんなにも美しいものなのかと、僕は呆けたようにしばらく見とれていた。 帰りの車の中でも、僕は興奮がさめやらずにそわそわしていた。 「今日はたくさん釣れてよかったね。僕も一匹釣ったし」と上機嫌になって云った。 「あれは釣ったんじゃなくて結果的に釣れたんだ。目印がぐいぐいと引き込んでいるのに気がつかねんだもの。それによ、川を渡ってくるときのあの姿勢はなんだ?」 思いがけない叔父の反応に、小さな胸はどきんと鳴った。 「でも、渓流魚は警戒心が強いから、決して水面に姿を見せちゃだめだって、釣りの本に書いてあったよ。」 僕なんかよりはるかに釣り歴の長い叔父が、こんな渓流釣りの基本を知らないはずはないのにと、不思議に思いながら僕は云った。 「ああ、確かにお前の云う通りだ。お前の云う事はたいてい正しいし、やることにも間違いが少ない。俺はな、それが気に入らねんだ。子供っていうのはな、周囲のことなんか気にしないで、じゃぶじゃぶと川を渡ってくるぐらいじゃないと可愛げがないべ。お前はあんまりにも色々と考えすぎる。もっと馬鹿で無邪気な子供になれよ。」 大好きな叔父から、可愛げがないと突き放されて、僕はひどく悲しかった。けれど、「正しい」という理由で怒られたことになぜか理不尽は感じなかった。確かに叔父の云うとおり、いまこうして思い起こしてみても、あのころの僕は妙にこましゃくれた、まったく可愛げのない子供だった。年齢に適(かな)わぬ心のありかたを、誰よりも気に病んでいたのは自分自身であり、それを他人に気取られることを僕は恐れていた。叔父の言葉に、ときおりひどくたじろいでしまうのは、それが粗雑で乱暴な内容だからではなく、すべて真実を言い当てているからなのだと、僕はそのとき初めて気がついた。 その日も叔父はふらりとやってきた。いつもなら玄関を開けるやいなや会心の笑みを見せる叔父なのに、その日は心なしか顔色がすぐれないように思えた。愛用している皮の茶色いバッグをたずさえているだけで、土産袋はどこにも見当たらなかった。 夕食の会話もいつもほどははずまず、食事が済むと、僕たち子供は他の部屋へと追いやられた。なにかただならないことが起きているに違いない。そんな胸騒ぎが、僕を不安にさせた。翌朝、ろくすっぽ話しもできないまま、叔父はあわただしく山形へ帰っていった。叔父が帰った後、いぶかる姉と僕を呼び寄せて、父は云った。 「アッキの会社な、危ねんだ。多分もうだめだべ」 世の中がバブルという虚栄の景気で沸き返るのはもう何年か後のことであり、日本経済は依然低迷を続けていた。社長業と云えば聞こえはいいが、叔父の営む小さな土建屋などは、仕事のほとんどが下請けかさらにその請負いであり、元受が一つ咳ばらいをしただけで、いつ倒産してもおかしくないあやうさの連続だったにちがいない。経営にいきづまった叔父が、何のために実家を訪れたのか、父に尋ねるまでもなかった。 「アッキちゃん、お金を借りにきたんでしょ?うちには貸してあげられるお金がぜんぜんないの?」 僕はそう云って父に詰め寄った。実の弟が窮地に立たされているというのに、手をこまねいているだけの父がなんともはがゆかった。 「どうにもなんね、だいたい借金の桁が違うんだ。」 父はそう云ったあと、いい聞かせるように僕の顔をねめつけた。 「どうだ、わがったが。魚釣りに呆けてばかりいるようなやつは、ろくな目にあわねんだ。」 理不尽な父の言葉に、僕は思わずかっとなった。けれど、父の苛立ちの半分は、おそらく自分自身に向けられたものなのだろうと気がついたとたん、反抗する気はたちまち萎えた。 それから間もなく、叔父の会社は倒産した。何事にも対しても始終毅然としていた叔父が、白いジープを手放すときだけ涙を流したのだと、従姉妹の祥子ちゃんがずっと後になってから教えてくれた。その後、家族を山形に残したまま、叔父は忽然と姿を消してしまった。叔母に聞いても居場所はわからなかった。本当は知っていたのかもしれないけれど、誰も詮索しようとはしなかった。 叔父が失踪して間もなく、借金取りが我が家にまでやってきた。黒い背広に身を包んだ二人組の男たちで、彼らは家族がみな揃っている早朝を見計らって何度か押しかけてきた。男たちが来ると、我が家ではいつも祖母が応対した。老人相手とあってか、彼らもさすがに声を荒らげるようなことはなかったけれど、抑揚をきかせた関西弁と鋭い目つきには、探るような狡猾さが感じられた。 「みなさんに迷惑ばがりかげで、もしわげねがす。」 ある日、祖母は深々と頭を下げて云った。貧しい時代を生き抜いてきた祖母の顔には無言の威圧がにじみ出ていた。なすすべがないと感じたのか、男たちは慇懃に頭を下げ、その後は二度と姿を見せることがなかった。 高校を卒業すると同時に、僕は家を離れ上京した。どうでもいいような専門学校をやる気がないまま卒業し、自然写真のエージェント会社に就職した。大都会で暮らすことを自ら決めたくせに、そこになじむことが出来ずに、山や海や川といった自然の情景をどこかで求め続けている自分が、なんだかひどく滑稽な存在に思えた。 若者たちでごったがえす渋谷の喧騒の中に会社はあった。事務所の窓から見える都会の空は、晴れた日ですらどこかねぼけたような水色をしていて、あまり好きにはなれなかった。それでも、秋の終わりの風の強い日などは、すっきりと晴れ上がった青空がどこまでも広がって、そんなときは羊雲が猛烈な速さで飛び去ってゆくのをぼんやりと眺めることが多かった。自分と同じ都会の空の下に、ひょっとしたら叔父もいるのではないだろうか。考えてもせんのないことがふいに思い浮かぶこともあった。 叔父に会ったら、話したいことは沢山あった。詩吟は中学でやめてしまったので、今では満足に詠うことができないこと。両親は反対するに違いないけれど、いつかは都会を離れて海のそばで暮らしたいと考えていること。小鹿のような黒い大きな瞳を持った勝気な女の子に恋をしているのだけれど、彼女にはすでに恋人がいて、成就させるのは難しいのだということ。そして最後にもう一つ。いつか叔父が予見してみせたように、自分の器量を考えると、どうやらたいした男にはなれそうもないけれど、それでもなにか自分にしか出来ない仕事を見つけて、精一杯努力するつもりなのだと、頭を掻きながら報告するつもりだった。 「俺が一番好きなのは〜 やっぱり美人のひざまくら〜」 今でも唯一頭に残っている詩吟が、昔叔父が宴会で披露した、即興インチキ節だというのがなんだか妙におかしかった。酒を飲むたびに父に詩吟をせがんだ叔父の気持ちが、今なら少しだけ理解できる気がした。  |
||
| 佐藤 敬太(さとう けいた) 渋谷で脱サラし、能登で漁師になった噂の(ごく一部でですが)敬太。夢は日本中の海をめぐって漁と魚の本を書くこと。著書に『なまこのひとりごと』(本の雑誌社刊)。http://kaizin.gogo.tc/ |
第1回へ | |