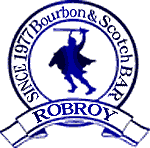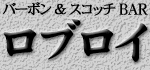今回は僕の昔話である。
20代前半、大阪時代の事である。
ある小さな駅から垂直に伸びている通りを、ほんの五分も歩くと右手に四畳半一間の安アパートが僕の住まいである。
それからまた五分も歩くと、ちょっとした飲み屋街があった。といっても通りの両端2〜3百メートルの間だけであったが。
ある日曜日の深夜、飲み友達と別れ、ふっと辺りを見回すと通りには誰もいない。一瞬時計が止まったように感じられた。
ほろ酔い加減の僕はアパートと逆の方へ歩いてみた。
飲み屋街はすぐに切れ、一軒の花屋がある。場所柄かまだ電気はついている。
その花屋を過ぎると、もうそこは飲み屋など縁のない世界に変わる。
いつもはこの辺で引き返すのだが、その日はそのまま歩いてみる事にした。
しばらく歩くと右手に小さい路地があり、その奥に白い小さな看板が見える。『バーきみこ』と書いてある。
何となく入ってみたくなった。ドアを開けると髪の長い色の白い子がポツンとカウンターの椅子に掛けている。
少しビックリしたような顔で「アッ、イラッシャイ」と言いながらカウンターに立つ。他に誰もいない。
「ご注文は?」の言葉に「スコッチのソーダ割りふたつ」と言うと「アラッ、アタシの分も・・・?」「・・・もちろん」
「ところで君が『きみこ』さん?」
というと、ここはオバの店で今日は知り合いの店の開店祝いに行ったとか、で今日一日だけ店番を頼まれたのだと言う。
それからもう一杯ずつ飲もうか、が何回か続く。
もう看板の火は消しているのだが、敢えて帰ってという素振りも見せないのでそれに僕も甘えていた。
とは言うものの、余り金は持っていないということと、ほどほどに酔ってきたという事もあり、帰ることにした。
帰り間際に、
「毎日ここで会いたいな・・・」
と言う。毎日君と飲むほど僕は金持ちじゃない、というと一杯でもいいし、あたしの分は自分で払う、と言うので次の日も来て見る。
彼女のいうとおり『きみこ』というオバがカウンターの中に立っている。彼女はというと、隅の椅子にチョコンと掛けている。
その横に僕は掛けると、何故かオバは優しい目で僕を見て「ウィスキーのソーダ割りネ」と、一杯つくってくれた。
そして次の日も、また次の日も、まるで時が止まったように同じ事が繰り返される。
やがて一ヶ月を過ぎようとしている頃、いつものようにドアを開けると彼女はいない。でもいつもの椅子に掛けると、
「ソメちゃんごめんね。あの子は北海道へ嫁にいっちゃったの・・・」
と言ってウィスキーのソーダ割りをつくってくれた。
その一杯を飲み干さないまま『きみこ』を出ると、一ヶ月前歩いてきた方へ目を向けた。
向こうに花屋が見える。灯りがいっぱい見える。僕は急ぎ足で歩き出した。