日独文化比較 5
ショッピング文化
ドイツへ出かけたり,そこに住む場合には,ショッピングが目的でなくても何か買うということは誰でも経験することになります。ツアーなどでお決まりの店に案内される場合は,日本語が通じるということもありますが一般的にはドイツ語でということになります。さて日本でも普及しているスーパーの場合は会話はほとんど要りませんが,大体入口と出口は別になっていて,出口からは入れず,また入口からは出られません。カートの類は鎖でつながれていることが多く,ワンコイン入れるとはずれます。元へ戻すとコインは戻ってきます。(因みに大きな駅などで乗客が自由に使える荷物運搬用のカートもこの方式が採用されています。)カートに買いたいものを入れレジに運ぶ点は日本と同じ方式ですが,レジでは品物はベルトコンベアーで順番に先へ送られる方式が普及しています。レジの金額を見て支払えばよいのでこの種の店ではドイツ語なしでも買い物はできます。ただ,間違いだとかクレーム,返品,交換の類は面倒なことが多く,大抵奥の別の係りに引き継がれ,いささか手間がかかる仕組みのことが多いようです。言葉も不自由だと,つい「まあいいか」ということになりがちです。
ところで最近話題の「レジ袋」は随分前から有料,ただし一度買えば何度でも使用できる丈夫なものです。大体日本の多くの都市のようにビニール袋にいれてゴミを出すという習慣は以前からありません。決まったゴミ容器にいれてだします。それを自動的に装着できるゴミ収集車が中味を回収します。この中味は今日4種類ぐらいに分類されています。レジ袋は単なるゴミにしかならないのでドイツでこれを使用しないようにするのは確かに環境に優しいでしょう。しかし日本ではレジ袋はゴミ袋として活用されているのでそれほど無駄にはなっていません。それどころかレジ袋より大きな環境コストのかかりそうなビニール袋にいれてゴミが回収されるわけですから,レジ袋を廃止ないし減量するといってもなんともこっけいな話です。業界も官界も大臣も勉強不足といわざるをえません。それよりこの関連で言えば「上げ底・額縁」といった「包装過剰文化」にメスをいれなくてはならないでしょう。昔からドイツではデパートなどで買い物しても簡単な袋にいれてくれるだけで,丁寧な包装は一切してくれませんでした。プレゼントなどの包装も別に用紙など求めて自前でというのが一般です。もちろん有料でならラッピングはしてもらえる場合はありますが。贈り物などの場合,日本の過剰包装がよく話題になります。ドイツ人は簡単な包装で満足します。スーパーなどで買った商品の包装を店で捨ててゆくドイツ人もかなりいます。包装も結局価格に含まれているわけですからドイツ人は過剰包装は「無駄」だといいます。日本人は「もったいない」という大変良い言葉をもちながら惜しみなく「湯水のごとく」包装に金をかけているといわざるをえません。最近の和菓子にこの傾向が強いのは興味ある現象です。手提げ袋,包装紙,外箱,小分けの小箱,個別包装などなど驚くほど「つつむ」ことに関心が払われています。小さなお菓子もこうして食べられない付加物で高価になるわけです。ドイツ人はそれをなかば軽蔑的に不思議がります。
店員が応対する一般の商店では,ドイツ語をこころえていると有利なことはいうまでもありません。一般的に英語も通じないことはないですが,やはりドイツ語の方が有利でしょう。ホテルなど割引があるような場合にも英語しか分からない外国人と見ると,だまって通常の値段を要求したりしてきます。これは誠実さという点では余りよいことではないのですが,時々経験することです。
ところで物価は日本のようにめまぐるしく変動することは少ないようです。リーズナブルというのでしょうか,ドイツ人のいうvernuenftigな価格が一般的です。極端に安い「メダマ商品」というのは余り期待できません。一桁安く見せようという心理は日本と共通しますが,100を99とするケースが目立ちます。日本では縁起をかついで98というのが好まれますね。文化の違いはこの場合は1パーセントでしかありませんが。物価といえば一般に食品は安い,ジュース類も日本の半値以下,生鮮食品も安価,売る単位もキロやポンド(だいたい半キロを1ポンドとよんでいます),一個単位は稀です。原則グラムなどの重量基準が用いられます。あらかじめ適量が包装されていないことも多く,必要量を客が秤にのせて選び,当該商品のボタンを押すと値札(商品やそれを入れたビニ袋に貼る)が印刷されて出てくる仕組みが愛用されています。従って野菜がキロ単位で売られているといっても,ものによっては,たくさんまとめて買わなくてはならないということは通常ありません。バナナも1本でも買えます。日本ではこのシステムは客が面倒くさがるとかで普及していませんね。(しかしその分手間賃やトレイ代などで高くなります。)バター,チーズも安い,ビール,ワインなども安い。意外に高いという商品は日常品では文房具類ぐらい。電気器具では洗濯機は温水が使用されるタイプなので高めですが,逆に単なる箱の冷蔵庫は一般に低価格といった具合です。
最近は日本の製品もたくさん売られています。(車やその他の高額商品もかなり愛好されています。多分価格も手頃なのだと思います。)ものによっては,うっかりお土産に買って帰ると「日本製」だったなどということもありますよ。
最後に手軽で安く他国では見かけない商品のひとつにWaschhandschuhというのがあります。大抵タオル生地でつくられた小型のなべつまみ風の袋です。これに石鹸をつけ顔や多分体など洗うのです。小回りがききごくわずかの布切れで間に合うところはドイツの節約精神にも通ずるように思います。使い勝手も良く,ともかくドイツ独特と思います。ドイツの小物や食品など,大抵のものは日本でも知られるようになりましたが,これはまだマイナーな存在でしょう。文化的な違いを知る安価な小物としてオミヤゲに面白いと思います。ご参考まで。ではまた。
日独文化比較 4
ドイツの郵便・電話など
ドイツの郵便事業の歴史は古いようですが,戦前の「帝国郵便」を引き継いだ「ドイツ連邦郵便」
Deutsche Bundespost は1989年までは国営事業でした。その後経過期間を経て1995年に完全に民営化され,旧連邦郵便は3社に分割され,郵便事業は「ドイツ郵便」,電話通信事業は「ドイツテレコム」,そして金融事業は「ドイツ郵便銀行」Postbank
に引き継がれました。民営化前には市内の諸所に郵便局があり大変便利でしたが,1995年以後はこれらはことごとく廃止され,大体,駅の近くとか市内の中心部の大郵便局だけになり大変不便になりました。小型の郵便物はポストにいれられますので,それほど不便ではありませんが,小包Paketなど大変不便になりました。また局員も削減されたのか,窓口で長時間またされることも多く,明らかにサービスは低下しました。もっとも元来ドイツの郵便局・銀行,そして一般商店も日本に比べれば接客態度はやや横柄な感じがします。これは今後もそんなに変わらないと思います。それはそれとして肝心の郵便代も高くなったようです。例えば,日本からドイツへ通常の封書の航空便は¥110ですが,ドイツからは1.70ユーロ(現在1ユーロ=¥156〜157)となっています。ハガキは日本からは¥70ですが,ドイツからは1ユーロです。高いですね。日本の民営化がこんなことにならなければよいのですが。
ところで郵便ポストは減ってはいないようですが,ポストは日本と違って黄色になっています。どうもフランス,イタリアなどもそのようです。赤いのは小生の記憶ではイギリスとオランダだったように思います。日本はその影響でしょうか。なお,ドイツ語では「ポスト」はBriefkasten
といいます。Postというと「郵便,郵便物,郵便局」の意味です。「どこにポストがありますか」と聞けば郵便局を教えてくれるでしょう。日本より前から使われていた郵便番号PLZは5桁,最近はヨーロッパ内では前にDが付されるようです。全般に番号枠は使用していないように思います。
電話は最近は複雑・多様になっているので日本との比較は余り意味が無いと思いますし,大体同じと考えていいでしょう。固定電話の新設,廃止は以前から簡単でした。公衆電話が減っているかどうかよく分かりませんが,少なくともコイン式はなくなりつつあると思います。プリペイドカード用はあると思います。ICが組み込まれていてしっかりしたカードです。カードは日本と違って裏側を上にして挿入します。これはATMなどほかの場合も確かめる必要があります。
システムの比較はさておくとして,電話のかけ方は日本人とドイツ人では大分異なります。まず無駄話はほとんどしない。そして通話はトランシーバー方式,一方が話しているときはだまって聞いています。相槌を打つということはほとんどありません。聞いているのかどうか心配になることがあります。ベルがなって電話にでるときも大半は簡潔に自分の名前を告げるだけです。例えば「田中です」は「tanaka!」でよいのです。初めてのところは私たちには本当に聞き取りにくいことが多いのです。もっともJa!とだけいって出てくることもありますし,たまにはHallo!もあります。車内の携帯電話もそういうわけでドイツでは余り他人の迷惑ということはなさそうです。多分,今でも常識的な自己管理で車内で通話可能と思います。日本人は長話+相槌と電話は騒々しい,だから車内では「マナーモード」にというアナウンスが必要になるのかと思います。小生はそんなにうるさいとも思いませんし,電話でなくても騒々しいご一行様は結構いらっしゃいますし,携帯電話にだけヤカマシイのもいかがなものかと思いますが,国民性の相違ですね。
因みにドイツテレコムは日本でも利用できます。ドイツへの通話は一時は一番安かったと思いますが,最近はどうでしょうか。
最後に貯金事業について,日本の郵便貯金は大変サービスがよいので大いに利用していますが,昔,ドイツの郵便貯金を利用した経験では,引き出し制限など結構細かい規則があって使いにくかった記憶があります。当時は金額などは局員がスペルを手書きしていました。最近はどうかわかりませんが,当時はサービスもそんなによくなかった,ただ駅の(あるいは近く)の郵便局では24時間出し入れ可能というサービスがあったように思います。それに反し「郵便振替」は便利でした。最近の事情には通じていませんが,どうも民営化以後は不便になったように思います。なお久しく日本から¥400でドイツに送金できた郵便振替も最近は5倍の¥2000に値上がりするなど,国際間のボーダーが無くなった一方で,さまざまな規制が強化されそれに伴い料金がかさむなど,なんとも奇妙な21世紀だと思います。ともかくも昔の方が利便性が高かったと思います。
日独文化比較 3
ドイツの公共交通機関について
ドイツの都市内部や近郊を結ぶ地域の交通機関としてはバスや市内電車,それに加えて大都会では地下鉄U-Bahnと高速鉄道S-Bahnが利用されます。バスは右側通行によるシステム以外は大体日本と同じと考えていいのですが,ときに見られる蛇腹部分で接続された大型車両は日本では無いようです。他方ロンドンでポピュラーな二階建バスはドイツではベルリン以外では見かけないように思います。乗車券は一般に自動販売機や運転手のところで購入,改札口(といっても無人)あるいは車内にある刻印機を利用して日付などを刻印します。後は乗車中は保持し,検札があればそれを提示します。しかし検札はめったにありません。乗客は信用されているという印象を受けます。もっとも万一有効な乗車券を所持していない場合は高額の賠償金を支払わなくてはならないという無言の圧力もあるかもしれません。降りるときには乗車券の回収はありません。ドイツ鉄道の利用とほぼ同じ感覚ですが,乗車時のみやや改札に近い感じになります。日本のバスや市電の場合は都市によって異なるようですが,先払い・後払いなどの相違もあるようですね。なおバス・市電などの料金体系は一般におおまかで日本のように煩雑ではありません。均一のことも多く,2ないし3段階程度のようです。これは近隣諸国でも同じであったように思います。日本のバスなどは細かすぎると思います。
ところで近郊高速鉄道など一部は1994年以降民営化Privatisierungされたドイツ鉄道DBが運営しているようですが,他の場合は地方自治体が関わっていることが多いようです。日本の国鉄はドイツより前に民営化されていますが,なぜ狭い日本で数社に分割されたのか,効率という点で理解できないところがあります。ドイツでは少なくとも旅客に関しては分割されていません。また日本の公共交通機関は地域によっては民間の株式会社が運営していることも多いようです。
市内電車は今日,排気ガスの問題からドイツでは推奨され愛好されていますが,一時廃れそうになっていた日本でも最近は見直されているようです。通常ドイツでは市内電車の乗降客は最優先されます。つまり原則的に市内電車が停車して乗降客がある場合,自動車は停止して待ちます。そういう点でドイツでは市内電車の利用は安全で便利,利用しやすくなっています。日本の法律もあるいはそうなっているのかもしれませんが,現実には道路の中央を走行する市電は大変利用しにくいようです。例えば九州の某市は友好都市ハイデルベルクから市内電車の車両まで輸入していますが,乗降客は特に優先されません。横断歩道の信号が青(日本文化は緑を青ともいいますので日本の信号は本当にだんだん青っぽくなってきています。西洋語では青信号は「緑」です)にならないと電車がきていても乗れません。もっとも車道が数車線あってそうでもしないと危険なのです。メインの停留所には歩道橋は設置されていますが,すべてというわけにいきませんし,バリアという点では大変です。要するに市電が共存しにくい道路状況といえましょう。他の日本の都市ではどうなっているでしょうか。ところでドイツや近隣国では2両あるいは時に3両連結した市電を見かけますが,これは日本では原則的には無いと思います。相違といえば相違でしょうか。
タクシーは日本のようにいわゆる「流し」はありません。一般に駅前や市内にあるタクシー乗り場Taxistand で乗ります。いない場合は無料の電話で呼べるようになっています。もちろん自宅などから電話で呼ぶこともできます。日本の一部の地方都市にある「お迎え料金」などは要りません。変わった習慣といえば,タクシーに一人で乗るときはよく運転手の隣の助手席に乗ります。恐らくこの席が一番よい席とみなされているからだと思います。因みに近隣諸国でも見かけますが,イギリス(ロンドン)だけは全く独特の構造のタクシーが使用されています。ドイツのタクシーは一般に大変親切,自発的に荷物など運んでくれます。そういうときはやはりチップが望ましいと思います。せいぜい端数のつり銭か日本円でいえば50〜100円ぐらいでよろしいでしょう。タクシーといえばドイツでは運転手に厳しい規制がないらしく?夏休みなどには学生アルバイトのこともありました。そういう時は残念ながら道をよく知らなかったりということもあります。しかし車はメルツェーデスのことが多く料金も適正,概してドイツのタクシーは快適なようです。因みに近隣諸国では頼みもしないのに,適当に回り道などという経験は結構ありました。日本では京都以外の大都市のタクシーは,概して不親切と思います。
因みに交通機関とはいえないかもしれませんがドイツにもエスカレーターがたくさんあります。これは日本に比べてややスピードが速いように思います。デパートなどでもそうです。これは国民性の違いでしょうか。思いつくままに記しました。ではまた。
日独文化比較 2
車社会の日独の相違
ドイツといえばまず車を思い浮かべる方が多いと思いますが,もちろん自動車発明の国ドイツは車社会という点では先進国です。ダイムラー=クライスラー社に名を残すダイムラーの試作車は1886(明治19)年に誕生しています。ご承知のようにアウトバーンもドイツ起源の装置です。現在総延長12000km, ちなみに面積がほぼ同じの日本の高速道路は,2003年のデータでは約7200kmのようです。この日本では,輸入車のなかで一般的にはドイツ車に人気が集まっているようです。代表格のベンツはドイツでは普通メルツェーデスとよばれていますが,ドイツではタクシーにも多く採用されています。その他アウディ,フォルクスワーゲン(VW),そしてベーエムヴェー(BMW)が知られています。最近輸入中止になったオペルもかつては人気がありました。しかし最近は逆にドイツの一般の市民の間では,日本車もかなり人気があるようになりました。
日本の高速道路では国際比較からみてもかなり高額の料金が徴収されますが,ドイツのアウトバーンは一般車は今でも無料です。そして速度制限はないと聞くと驚かれるかもしれません。推奨速度はあっても一般乗用車には速度制限はないようです。運転者の判断にゆだねられているわけです。安全運転の鉄則は低速という考えは余り支持されていないようです。経済速度は話題になりますが環境保護先進国であるにもかかわらず,自動車原産国のプライドの方が先行しているような感があります。あるいは一種の合理性に基づいているかもしれません。大体,昔から適度のスピードで走行し他車と調和的に走行することが勧められていました。さすがに一般道路には速度制限がありますが,通常市街地から出ると最高100kmとなっています。市内は50kmが原則,特に定められた道路では30km程度といった具合です。しかし他方,生活道路などでは通り抜け禁止のために「関係者のみ通行可」という制限がよく見られます。
もちろん運転免許制度はドイツにもありますが,日本と違うのは一度取れば書き換えなどという手間のかかることはしなくてもよいという点です。日本のシステムになれている人々は首を傾げたくなるかもしれませんが,1964年に取得した小生の免許は今も若いときの写真のままで有効なのです。少なくとも7,8年前はそうでした。免許をとるときも日本で言えば仮免許が最初からでるようなシステムです。ドイツにも自動車運転免許教習所,いわゆるFahrschuleはありますが箱庭式の練習コースなどはありません。そのためドイツには自動車教習所がないと勘違いする方もあるようです。ただ学校といっても1部屋だけということが多くそこでは主として法規を学びます。これは日本と同じです。では実技はというと最初から路上で練習します。先生が右側に乗り,練習者は左(ブレーキは両方にある)に搭乗して毎回小1時間というのが標準です。1ヶ月から2ヶ月の練習で実技が習得できたと先生が判断すると,後部座席に試験官が乗って実技試験,いつも回る路上コースを1順,握手を求めてくれば合格となり,その場で免許証を渡してくれます。これはかなり昔の経験ですが,聞くところでは原則は変わっていないとのことです。ドイツ語の勉強にもなりましたが,いろいろな意味でよい勉強にもなりました。日本に帰ってから,日本の免許証に書き換えてもらいました。因みに日本発行の国際運転免許証はドイツでも有効だと聞いています。
日常の車のコミュニケーションは右側通行(イギリス以外のヨーロッパは右側通行)という点を除けば,原則的には日本と変わりませんが,細部では大分違います。何より気をつけなければならないのは交差点での進入優先権といいますか,簡単にVorfahrtと称していますが,これには注意が必要です。信号や標識のある交差点ではそれに従えばいいのですが,見落とさないように十分に気をつけなければなりませんし,何もないところでは,規則によって判断しなくてはなりません。歩行者が最優先されますが,車類は大体右側優先となります。日本の地方都市などでは,このあたりは,かなりあいまいなのですが,そのような習慣は通用しません。そうかといって無視すると衝突するというわけではありませんが,かなりの罵声を浴びる可能性は十分にあります。車線変更もルールに従わないと同様な目にあいます。また日本人はセンターラインにそって走行する方が多いようです。ドイツの原則はできるだけ右によって走行という次第です。これは道路事情にもよりますね。日本ではあまり左側に寄れません。違いといえば違いでしょうか。そういえば信号は赤から緑に変わる前には赤黄が同時に点灯して準備を促します。最近日本でも類似の信号はあるようですが一般的ではないようです。
細かい相違のひとつにライトによる合図があります。ドイツではLichthupe(光のクラクション)といいますが,これはどちらかというと警告のことが多いようです。日本では譲ってくれるときにもよく用いますので注意がいるでしょう。もうひとつドイツ人は渋滞などのときを除いて,車間距離は特に高速道路では日本人よりも広く取っています。日本人が失敗しやすいのは追い越した後車間距離をとらないで前へ入ることです。日本の高速道路にはところどころ車間距離を確認できる装置まで準備しているのですが,余り活用されていない。昔,ドイツで日本人が大事故を起こしたケースがありました。日本では高速道路を含めて車間距離が狭いと感じます。飲酒運転が最近社会問題になっていますが,普段から車間距離を十分とらないという運転習慣も一般の事故にはかかわっているでしょう。ところで飲酒運転の悲惨な事故に関する報道は,ドイツのメディアではみかけませんが,現実はどうなのでしょう。こうしてみてくるとドイツのドライバーは安全運転に心がけているようですが,かと思うと霧などで視界がほとんどない高速道路の走行など時に無謀かなと思うような状況もないわけではありません。なおやや日本人に不慣れな走行方式にロータリ風の環状通行Kreisverkehrというのがあります。数本の放射状の道路がリング状に結ばれているようなところで定められています。ルールをわきまえていないとなかなかリングから抜けられません。まだ細かいことはいろいろありますが今日はこの辺で。
日独文化比較 1
日独鉄道旅行事情比較
ヨーロッパでは車窓の風景を眺めながらの鉄道の旅は高速鉄道の時代でも魅力を失っていません。日本の新幹線は,残念ながら,高速と引き換えに,場所によってはトンネルが続き,高架の部分も防音壁などに遮られ,車窓の眺めが楽しめるという状態ではないところが増えています。その点ではヨーロッパの鉄道事情は,いわゆる新幹線区間でもまだまだよほど余裕が感じられます。風景の美しさは主観的な部分もありますし,普段見慣れた景色とは異なる異国の風景には惹かれるという面もありますが,ヨーロッパには「絵のように美しい」というツーリズム広告の愛用語がまさにぴったりの車窓の眺めに恵まれた路線が多いように思います。ドイツではライン川沿線,南ドイツの山岳地帯,オーストリアのグラーツからインスブルックを経由してチューリヒへ向う路線,とりわけスイスのインターラーケンからルツェルンへ通ずる路線などが印象に残っています。
ところで車窓の眺めが楽しいだけではありません。車内もゆったりとしていますし,わが国の新幹線車両の5列の座席にはお目にかかったことはありません。1等は大体3列,2等は4列,コンパートメントタイプとオープンタイプが適宜に混在,好みの座席を選べることが多い。そして何より静かで落ち着いた雰囲気が好ましいのです。振り返ってみると,いわゆる「アナウンス」の類が駅のホームでも車内でも必要最低限,時には必要以下―これは困ることもありますが―なのです。急行以上の列車には,到着・発車時刻や乗り換え案内のパンフレットが座席に配布されていて,それを見れば分かるようになっています。もっとも事故・故障の場合はいくらかアナウンスがあります。これは日本でも分かりきった情報のアナウンスが多い割には少ないようです。もちろん「指定席の入り口から自由席に入らないように」などという類のアナウンスは聞いたことがありません。文化の違いか,マナーの違いか,JRによるとお客様の要望でアナウンスしているということです。日本の駅は騒々しいと思います。ヨーロッパから帰国するといつもそれを感じたものです。
もうひとつドイツおよび近隣諸国ではいわゆる「改札口」というものがありません。駅構内へは自由に入れますから,入場券などというものもありません。見送り,出迎えも気軽にということになります。改札口がないということは,いちいち切符を見せるというわずらわしさから私たちを解放してくれます。ただし車内の検札は必ずあります。でも車内では座席に座りながらゆっくり切符を見せ,ついでに到着時刻や乗換えなどについて情報を得ることもできます。乗客は大変信頼されているようで心地よいのです。日本の場合,例えば熊本と金沢の間を旅行すると改札が4回,車内検札が2回(つい最近まで3回でしたが最近山陽新幹線の車内検札は廃止になった)これはかなり面倒なことです。人件費節約から自動改札などを発明したのでしょうが,荷物などもっていたり,同行者の分をまとめてというような場合大変煩雑で機械は人的なサービスの代わりはしません。経済優先で,乗客を丁寧に扱っているとはいえないのではないでしょうか。「美しい国日本」ということを言う前に国民がもっと大切にされ幸福になるようなシステムを官民あらゆる分野で心がけるべきではないでしょうか。
日本でもJR西日本の山陽新幹線のレイルスターという列車にはグリーン車はありませんが,普通車指定席は4列です。例外的には他にもあります。またレイルスターの4号車は「サイレンスカー」となっていて始発駅と終着駅以外アナウンスはありません。車内販売もだまって通過して行きます。これはドイツ並みに静かな車内を提供していますが,例外的な存在です。車内販売といえば,ドイツなどではこれは期待できません。よく利用される方は不便ということになります。ごくわずかの列車でしか見られません。またドイツの新幹線ICEでも昼食時に軽食を売りに来ることがありますが,余り期待できません。国際特急などには食堂車はありますが,以前ほど充実はしていません。もっとも車掌が「コーヒーいかがですか」といってくる列車もありました。ご参考まで付記いたします。
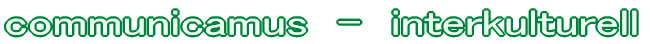
前のページへ 最初のページへ 次のページへ
お願い: 本ページの写真・テクストの引用は関連法律で認められている範囲内でご利用ください。
日独文化比較に関するコラム風の拙文を掲載しますが,その他の関連のエッセイ・小評論・書評など
適宜ご覧いただく予定です。よろしくお願いいたします。
![]()