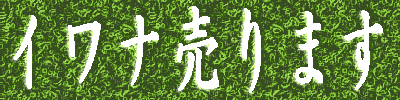 |
 |
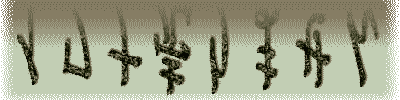 |
 |
| 河崎 徹 | |
| 河崎さんは、金沢近郊の医王山(いおうぜん)で、イワナやヤマメなどの養殖と、川魚料理の店「かわべ」をやっている、そろそろ落日間際の六十代。仕事より、魚釣りやら草野球やらにうつつを抜かし、店の方は、気が乗らないと勝手に閉めてしまうのが玉にキズ。(でも料理はウマイんだな)。いつもマイペース、ままよ気ままの行きあたりばったりエッセイからは、その人柄が伝わってきます。 |
|
| 第六十二回 「人間(とは)」 |
「もう生きていたくない。早く死にたい」、高齢(九十一才)で生活の心配のない高額(私からみて)の老人ホームに入っている私のおばさん、にあたる人は私がたまに面会に行くと、私に向って言う言葉は、この言葉ばかりである(私の母親(九十三才)も同じである)。それを聞いて私は言う。「そんなに、いそがなくても、どうせその内お迎えが来る、それまで何でもいいから楽しい事を一つでも見つけて生きていかなければ」と、毎回同じ事を言って室を後にする。室を出るといつも自分の言った言葉に、むなしさを感じ憂うつな気分になる。「長生きするという事はこんな事なのか、私もいずれこうなるのか、今の私はこうなる人達の予備軍なのか、私はこんなのはいやだ」。そのおばさんがインフルエンザの後遺症で緊急入院したという報せが私の所に入った。仕事が終ってからすぐ病院へ行った。受付けで病室を教えてもらい、その室へ入った。六台のベッドがあり、六人の老人(女性)がベッドにそれぞれ居たが、皆、点滴、栄養袋をつけ、まったく動く気配がなかった。その中の一人、おばさんのベッドに近づき、そっと顔をのぞき込んだ。しかし何の反応もなく、顔色も悪く、たぶん眠っているのだろう。介護士の話しでは意識はあるというので無理に起こすのは気が引けたので、声をかけずにそのまま、室を出た。それからナースステーションにより、おばさんの病状を少しくわしく聞き、介護士の方から、これから(明日から)検査に入る、という事を聞かされ、「患者(おばさん)が体に付けている器具を勝手にはずす危険があるので、手足を拘束する事に身内のあなた(私)に同意して(サインして)くれ」と言われ、「仕方なく」サインをした。夜間誰れともすれちがわない病院の通路を一人歩きながら、やはり重たい気分になっていた。「もう生きていたくないという人間に、今さら検査して何になる。手足を拘束までしてどうしようというのだ」。数日後、我家の娘をつれて、おばさんの見舞いに行った。「今回は危ないかもしれない(以前にも、そういう事はあった)」と私の兄からの連絡があったし、私もなんとなくそんな気がしたので、おばさんとはよく面識のある娘をつれて行った。「こんな所(病院)で死にたくないな」と思いながら、おばさんの病室に入った。同じベットの上で、同じ状態(点滴、栄養袋、それに手に大きなグローブをつけ)だったが、前回とはあきらかに雰囲気が違っていた。少し離れた所からでも顔色がいいのがわかり、何よりも違うのは「動く」気配が感じられた。娘が「おばさん」と声をかけたら、目を開け、娘の名前を言った。それは弱々しかったが、前回の時のように目も開けず、物も言わず、苦痛にゆがんだ表情ではなかった。「いつも世話になってすみませんね」、元教師だったおばさんらしい言葉だった。「前に来た時より元気になったね」などという話しをして、最後に「もう少しの間、ガンバッテ、四月になったら、又、去年の様にいっしょに桜の花を見に行きましょう」と娘が言ったら、うれしそうな顔になり、にっこり、うなづいた。おばさんの体調も気遣って、わずか十分ぐらいの面会で病室を出た。今回も夜間の病院の通路は私達親子以外通る人もなかったが、今回はいつもの私のあの沈んだ重たい気分におそわれる事はなかった。娘に「何かおいしいものでも食べに行こうか」と言って病院を出た。 追伸 今年の桜を見る事なく、おばさんは旅立っていった。三月十五日、享年九十、主治医によれば「最期まであばれる事もなく、おとなしい患者だった」と。今は金さえあれば何でもできるといわれる時代だ。もっと好き勝手にできたものを、それが戦前、戦中と戦後を生き抜いた女の意地というものだったのだろうか。 「おわったね」、もの言わぬ故人(ヒト)に、我が言う。 |
| 第六十一回へ 第五十回特別編 詩「今」 |