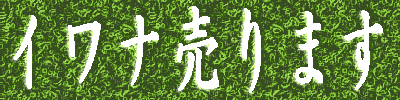 |
 |
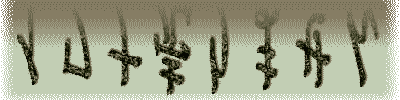 |
 |
| 河崎 徹 | |
| 河崎さんは、金沢近郊の医王山(いおうぜん)で、イワナやヤマメなどの養殖と、川魚料理の店「かわべ」をやっている、そろそろ落日間際の六十代。仕事より、魚釣りやら草野球やらにうつつを抜かし、店の方は、気が乗らないと勝手に閉めてしまうのが玉にキズ。(でも料理はウマイんだな)。いつもマイペース、ままよ気ままの行きあたりばったりエッセイからは、その人柄が伝わってきます。 |
|
| 第七十回 「私をスキー(フランス)へ連れてって (後)」 | |
真冬の晴れわたった空、雪におおわれたアルプスの山々が連なる光景の中、どこからともなく一台のヘリコプターが現われ、わずかに平らになった尾根の一角に舞い降りた。そのヘリコプターの中からスキーを肩にかつぎ、サングラスをかけた一人の男が雪面に降り立ち、雪の感触を確かめる様な足どりで十数歩歩き、ヘリコプターから離れたと同時にヘリコプターは青く澄みわたった真冬の空に舞い上がり、やがて視界から消えていった。男はすぐにスキーをはき、金具の具合を確かめ、スキーヤーならだれしもよくやる様に二本のストックを体の前で「カチカチ」と打ちならし、二本のスキー板を片方ずつ前後にすべらせ、準備万端スタートの態勢に入った。だがその後、ほんの一時、かけていたサングラスをはずし、まぶしそうな目をして空を見上げ、それから周囲の山々山々を見渡し、再びサングラスをしっかりかけ、これから滑り降りる前方の斜面をしっかり見すえた。そして大きく深呼吸をして意味不明のかけ声を発し、急な斜面に二本のシュプールを描いて滑り降りていった。 今から三◯年ほども前のスキー全盛時代、どこか(たぶんスキー用具メーカー)のテレビコマーシャルの一場面である。このコマーシャルを見ていた私(当時は若かった)は、一度あれ(コマーシャル)をやってみたいと思っていた。 私がスキーを始め、そして今でもやり続けているのはなぜだろう。近くにスキー場(小さな)があったからだろうか、冬場は仕事が少なくヒマだったからだろうか。長年やっている内に、すこしはスキーのおもしろさがわかったからだろうか。スキーブームが去って仕事がヒマで、しかもこの辺ではめずらしく晴れた日にここのスキー場に行くと、平日なら十数名ぐらいしかスキーヤーがおらず貸し切り状態であった。リフトで頂上まで行き、そこからは遠くの山々や、日本海までも見渡せ、どこか別の世界にいる様な気分に浸っていた。 雪面に 一人立つ 我は何者ぞ 簡単に言えば雪国で過ごす私にとってスキーをする事が自然と生活の一部になってしまったのかもしれない。だが肝心のスキーの技術が上達しない。それでもここのスキー場の最大の難関三十数度という急斜面にも挑戦し続けてきた。いつも急斜面を前にして「もしここでコケてケガでもしたら」という思いが頭をよぎる。又、周囲からはいつも「イイ齢をしてケガでもしたらどうするの」といわれながら今まで無事やってきた。私だって勝井(龜鳴屋主人)のホームページで「そろそろ落日間際の六十代」と書かれるまでもなく、周囲からは年寄り扱いである。ただこの頃では「あのジイサン(私)、何をさせても、もうダメ、ただスキーをはいたら、とたんに、死んだ魚の様な目が急に輝き出し、体がしゃきっとする」というのが目標である。ほとんどの事が人生途中で挫折したが、幸いにもいくつかの趣味だけはかろうじて残っている。その一つ、スキーの集大成としての「アルプス山頂からのスキー滑走」である。(そんな大ゲサなものかな) フランスへ行くのに「フランス語、大丈夫?」「フランスは芸術の宝庫よ、どこの美術館へ行くの?」。そんなことは知るか。私がフランスへ行くのは「スキーだけでいいのだ」。老いの一徹(わがまま)である。 私、「オリビエ君、日本では『速い男はキライ』と言われる。だからゆっくり行って(滑って)」、「オリビエ、もっとゆっくり行って(滑って)」、「オリ、待て!」山頂からいっきに滑り出した彼(オリビエ君)の姿は見る見るうちに小さくなって谷底の方へ消えていった。「日頃(日本にいる時)は口数少なく、穏やかで哲学好きのフランス人と思っていたのに、奴は単なるスピード狂ではないか」とブツブツ文句を言いながら必死に彼の後を追った。待ちに待った(このためにフランスに来た)スキー。ゴンドラ、リフトを乗りつぎ、最後は昔なつかしいロープを股の間にはさみ、尾根づたいに標高二千数百メートルの山頂(終点)まで来た。(途中、股の間にはさんだロープがうまく扱えずに転倒し雪の中でもがいていた私を立派な体格(?)の女性が軽々と抱きかかえて助けてくれた) 山頂(終点)の景色は何十年も前にテレビで見た景色である。青空をバックに純白の山々(アルプス)が見渡すかぎり連なっている。たぶんあれが「モンブラン」だろうという、きれいな山をバックに記念写真をとった。私達の出発地点は山頂なので木は一本も無く、所々岩がむき出しになっている。私達が来る数日前にどこかの国の有名なカーレーサーがやはりアルプスのスキー場の岩二激突して大ケガをしたというニュースがあり、一応コースはあるものの、本当にうまいスキーヤーなら三六◯度、どこでも岩をぬって滑る事ができる。私達が滑るコースの横に網で両側をかこった滑降コースがあり、見ていたら、ヘルメットをしたスキーヤーが時速100キロぐらいかと思われるスピードで、「あっ」という間に私達の横を通り過ぎて行った。「オジサン、私達もやってみましょうか」とオリビエ君。私「いやだ、まだ死にたくない」。ここ(スキー場)へ来て水(雪)を得た魚の様なオリビエ君、「それでは行きましょう」と言うやいなや滑り出した。彼の姿が谷底に消えていった。雪質は最高(気温が低いから)、コブはほとんどない。転んでも、変な転び方はしないだろう。コースも広いので他人(ヒト)にぶつかる事もないだろう。又、スノーボーダーも少ない。オリビエ君の話では、「アメリカ発生のスポーツはフランス人はきらい」なんだそうだ。「以前経験したボーダーとの接触もないだろう」という。頭の中でいろんな事を想いめぐらしながら、今まで経験した事のない様なスピードで後を追ってもすぐに離される。ここフランスでは、日本(私の知っている)スキー場の様にスピードを殺して滑っている様なヒトはまずいない。(フランスではアルペン競技で一番人気は滑降であると)「井の中のカエル」の様な私とちがって、いつも大海で滑っているカエル(オリビエ君)は、スキーを教えていた事もあった父親に連れられ子供の頃からこのスキー場でへ来ていたというのでさすがにうまい。(カエルの子はカエル)必死で後を追い、少し彼(オリビエ君)に私が近づいたのを確認すると、彼は又私を引き離す。「彼はそんなに私と滑るのがいやなのか。日本に居る時、そんなに彼をいじめたか。私を捨てないで」。それでも騎士(武士)の情けか、コースが交差する要所要所では私を待っていてくれた。(コースをまちがえると、とんでもない所へ行ってしまう)どうにか下まで滑り下りて別のコースを三度ほど滑ったところで「もう十分楽しんだ(限度)。これくらいで終りにしましょう(これ以上やると日本へ帰れなくなるし、とは言わなかった)」出発前の(日本での)妄想とはかなり違った。(晴れた屋外のテラスでのんびりとワイン、コーヒーを飲み、ゆったりと時を過す―観光用パンフレット)まず天気がいいとは限らない。アルプス頂上では、ゆったりと屋外にはいられない。(−10度以下、又、直射日光が強烈)が、今までにはない体験、特にかなりのスリル(恐怖心とも言う)も味わった。滑り終ったオリビエ君「又、フランスへ来ましょう。その時はパリなどに寄らずにスキーだけしましょう」私「同感。ただし、もっとゆっくり滑ろう」 目的のスキーもどうやら無事に追え、私が泊めてもらったオリビエ君の親類の山荘(別荘)で歓迎(お別れ)のパーティー(私の最もニガ手)も、話し好きなフランス人相手に「メルシー、ボンジュール」の二語だけで乗り切った。(旅の恥はかき捨て)ワインだの、フランス語、ダメ、日頃(日本でも)から不相応。それを知ってるサチコさん「このパーティーは、あなた達のためですよ、敵前逃亡はダメ」とクギをさされたので、オリの中のクマの様に、用もないのに室の中をウロウロ歩き回り、エサ(ゴチソウ)が出れば食べるだけ、という有様だった。いっその事、トイレの中にかくれていようかとも思ったが、お客はワインをがぶがぶ飲んで、トイレによく行っていたので、それもできなかった。そのおかげ(?)で、その晩は心身ともに疲れ、旅行中ずっと続いていた時差ボケもなく、はじめてゆっくり眠れた。 帰国の日、ずっといっしょにいて、すべての面倒を見てくれたオリビエ、サチコ夫婦、それにまだ一才少し前のサオリ(日本名)ちゃんとリヨンの新幹線の駅で別れた。(少々不安になる)来た時(パリからリヨン)はもう夜だったので外の景色は見なかったが、帰りは午前中で外の景色をゆっくりとながめる事ができた。オリビエ君は「ぼくはフランスの田園(農村)の風景が好きです」と言っていたが、私もゆったりとした農村の風景はパリに着くまであきずに見ていた。その後は(パリから)来た時と同様、ただ忍耐だけの飛行機の旅だった。(私は「飛行機が好き」という人間には無条件で友達になりたくない) 地元飛行場(小松空港)に到着し、駐車場にとめてあった自分の車に乗って一息ついたとたん、ドッと疲れを感じた。旅行中ずっと禁煙していたタバコに火をつけ、しばらく向う(フランス)と同じ様な天気の小雪の降る外の景色をながめていた。フト、「この十日間(旅行の日)はなんだったのだろうか。まあ落ちついてから、ゆっくり考えるかな」と自動車を動かし、久しぶりにカセットテープの音楽を聞く。吉田拓郎。「わたしは今日まで生きてみました…そして今わたしは思っています 明日からもこうして生きて行くだろうと」 (付記) 今回は旅行日程、すべての手配(ホテル、飛行機、新幹線…)、彼の実家、彼の親戚の山荘等の宿泊のすべてをこの年寄りのためにオリビエ、サチコ夫婦がやってくれた。又、一才にも見たない子供を抱っこしてパリの観光、ガイドまでやってくれた。言葉、フランスの習慣のわからない私には彼(彼女)がいなかったら、今ごろはパリの街角で言葉も話せず、「物乞い」をしているか、地下鉄のベンチで寝起きしていただろう。又、フランス人の習慣、お互いの挨拶「ハグ(抱擁)」では、オリビエ家の人達に「変な外人」と映っただろう。最初私が恐る恐るやっていたら、サチコさんから「もっと気持をこめて」と言われ、少し慣れてオリビエ君のお母さんにハグと同時に耳もとで(相手は日本語がわからないと思って)、「少し体重を減らしたらいいよ」と言って、マタ「フランス女性になんと失礼な」と叱られた。又、オリビエ君の祖母(九十才ぐらい)に思い切りハグをしたら、「危ない、そんなに力を入れたら、骨が折れる」とこれまた失敗した。「愛情表現の豊かなフランス人と、子供の頃から、ゆがんだ愛情表現しか教育されてこなかった私(日本人)とのちがい」としておこう。私よりしばらく遅れて日本にもどってきたオリビエ、サチコ夫婦にフランスで世話になったお礼を言わなければ、といろいろ考え、「ここはフランス流の気持を込めたハグを」と一大決心をして夫婦にハグをした。そしたらサチコさん「オジサン、まだ時差ボケ、フランスボケ、それとも本ボケ」
|
|
| 第六十九回へ 第五十回特別編 詩「今」 |
|