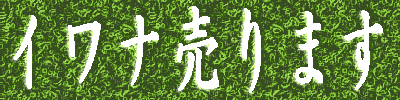 |
 |
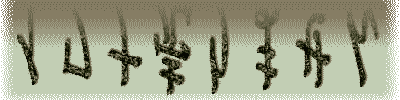 |
 |
| 河崎 徹 | |
| 河崎さんは、金沢近郊の医王山(いおうぜん)で、イワナやヤマメなどの養殖と、川魚料理の店「かわべ」をやっている、そろそろ落日間際の六十代。仕事より、魚釣りやら草野球やらにうつつを抜かし、店の方は、気が乗らないと勝手に閉めてしまうのが玉にキズ。(でも料理はウマイんだな)。いつもマイペース、ままよ気ままの行きあたりばったりエッセイからは、その人柄が伝わってきます。 |
|
| 第七十一回 「鮎釣りの話とヒトコト余計な一文(前篇)」 |
朝、娘を電車の駅まで送って近くのコンビニで100円コーヒーを飲む。飲みながら、今日、どの場所で釣ろうか、と考える。「あの名人らしきオヤジの入った場所の後では、たぶん私にはムリ、昨日私がよく釣った場所は今日は朝早くから他人がもう入っているだろう……」といろいろ考えをめぐらす。ここ金沢市近郊では、犀川、浅野川という二本の川が鮎釣り対象の川である。いずれも川幅、水量とも私が若い頃(大学生)よく通っていた東北の川に比べ規模は小さく、向う岸へ渡れるくらいの場所である。したがってよく釣れる場所となればおのずと限られて、私が釣り場へ着く頃(10時頃)にはもうその場所には誰かが入っている。「他人(釣り人)がいなくて、私だけしか知らないよく釣れる場所」なんていうのは私だけでなく釣り人の誰れもが思う事だろうが、現実はそう甘くない。そんな状態だとわかっていても、今日入る(釣る)場所を決め、コンビニのオニギリ二個とお茶を持って、釣り場へ向う。これが私の毎日の始まりである。 「釣りはいいが、お前、自分の仕事(養殖業)はどうした」「そう、仕事はやめました」「なんで」「この先どうする」。周囲の人から、矢継ぎ早に心配(?)の声が飛んで来た。 去年の夏、ある日突然、養殖をやりたいという人間が現われた。私のこの場所(養殖場)では二人でやれるほど利益はでない。ならば「私がやめ、お前が一人でやれ」という事で、早々に私が引退する事をきめた。そう言えば、昔、大学をやめた時もそうだった。「やめたら、すっきりするだろう」「もっと他の道(好きな事)ができるのでは」であった様だ。先の見通しなど何もなかったあの当時は今よりもっときびしかった。当時、最も心配(?)していた母親も二年前に亡くなり、我妻も、もうあきらめた(?)様で文句は言わなかった。 私達老人にとって今の社会(格差社会)は三種に分類される。一番下は、その日の生活に四苦八苦している人、その次は当分(今の私の場合は一年間ほど)の余裕のある人、一番上は死ぬまで心配しないでよい(金が手に入る)人である。世界中見わたせば一番下の人が多く、私の様に中は、まだいい方だろう。上流階級の老人が金とヒマにまかせて釣りをするのならバチ当りの感がするが、中流下流を行ったり来たりする私の様なものが一年間釣り(鮎釣り)に夢中になったくらいでバチも当るまい。(御託を並べても字のごとく自分だけで誰も納得してくれない) さて本心は「釣りたいから始めた」。四十年ぶりくらいの鮎釣りだったが、当時とはかなり異なっていた。当時は地元(山間部)の人達が、ねじりはち巻、ハッピ(漁協)姿で竹の一本竿で腰まで水につかって釣っていた。ところが、私が解禁日、鮎釣用鑑札を買って、いざ河原に下りていっておどろいた。ほとんどの釣り人が上から下まで釣り雑誌に出ている「鮎釣りスタイル(上は鮎釣り用救命胴衣、下はすべり止めぐつと一体となったタイツ)」である。しかも竿は10メートルを越す様な長く軽いものである。(その日私の竿は5メートルであった)翌日釣り具店へ行って、その値段におどろいた。ほとんどが十万円以上であり、店員いわく「今の高齢者の方達はお金持ちですよ」と。私は無言で何も買わずに店を出た。「釣りは道具じゃない。運とカンの世界だ」と自分に言い聞かせ、前日と同じスタイルで川に入った。オールドファッションにもかかわらず、又何十年ぶりにもかかわらず結構な釣果があった。あの野鮎がオトリに体当りして、釣り針にかかり、一気に下流に下る。それに合わせ自分も必死に下流に下り、やっとの思いでタモ網に鮎を取り込んだ時の感激がよみがえった。ただそれにしても、四十年のブランクはやはり大きかった。かなりの流れの中での移動は足がもつれ、しかも鮎の食するコケがはえた岩の上は滑り、何度もころびそうになる。(実際ころんだ)さらに困ったのは、その当時と比べやたらと糸が細く鮎に見られないのはいいが、私にも見えない。川の真ん中で糸がからみ(ヘタクソ)、流れに抗して竿を肩にかつぎ、それを直すのは今の私には至難の技である。思わず「トシやなあ」と一人言を言うし、カンシャクを起こし、「今日はやめた」となる事もある。ほかにも「今日はやめた」となるのは、鮎釣りには欠かせないオトリ鮎が衰弱して川にいる鮎の気を引かなくなってしまう時である。死に体の鮎を引きずりまわし「根性のない鮎」とののしり、(釣れた時は「ごくろうさん」といって釣れた鮎ととりかえる)あきらめる。「鮎の友釣り」とは釣れた鮎を見て「何ときれいな魚」と思う反面、すぐそれ(鮎に)に、鼻かん、送バリを打ち、引きずり回すのだから、残酷な所業である。 さて、期待と不安、さらにおどろき(今の鮎釣りスタイル)で始まった私の鮎釣りだが、出だしは前記したように、予想以上のものであった。知り合い(私が仕事をやめるのに文句を言っていた)や、我妻に「鮎を食べる」と持って行けば、「天然の鮎」と喜ばれ、非難の声もうすれていった。それで「これからは心置きなく鮎釣りができるぞ」とほくそえんでいた矢先、ばったりと鮎が釣れなくなってきた。 「なぜ、どうして、私のどこがいけないの」。私も昔は一応生物学を修めた(?)人間のはしくれである。(私が何か都合が悪い時に(自分を正当化するため)使う常套句である。学歴の正しい(?)使い方)。昔(大学生の頃)鮎釣りを始めた時、宮地伝三郎(京大教授)の『アユの話』を熱心に読んだ。(つもりだった)今では相当あやしげになった記憶を必死にたどり、いろいろ工夫してやってみたが、やはり鮎は釣れない。その内、私が通っていた浅野川での釣り人の数がめっきり少なくなっていった。どうも原因は私の「釣の腕」だけではないだろうと思う様になった。あの当時(『アユの話』の時代)は鮎と言えば天然遡上(川で産卵し、卵からかえった稚魚が海に下り、翌年再び川にもどる)の鮎か、湖産(海にもどらず琵琶湖かそれに連なる河川で一生を過す)鮎の二種類(本当は両方は同じ種である)であった。それが現在、新たに卵から養魚場で育てた養殖そのもの鮎が放流されて話はむつかしくなった様だ。橋の上から見ていると群れた鮎が結構いても、いっしょにながめていた釣り人は、「あれ(鮎)は、なわばりを持たない鮎で友釣りでは釣れない」と言う。『アユの話』でも「群れ鮎」の事は載っていた様だったが、それ(鮎)は、「なわばりを持ちたくても持てない弱い(?)鮎で前任者(魚)がいなくなれば(釣られたら)そこに入って来る」と確か書いてあった様だ。だが卵から育てられた養魚場育ちの鮎は放流されて初めて自然界に出て時間が過っても、なわばりを持とうとしない。いつまでも大勢で群れたままの生活をつづけている様だ。したがって私が釣っていた川(浅野川)では湖産鮎と養殖鮎を放流していて(海からの天然鮎は下流の川の状態からしてほとんどいないだろう。(推測)私が最初によく釣れたのはたぶん湖産の鮎で、それがもういなくなって、いるのは養殖鮎で私には釣れないという事らしい。それでも「何かの拍子に養殖鮎が、なわばりを持つよになるかもしれない」と数回出かけて行ったが釣果はなかった。「そんな養殖鮎でも釣る方法があるらしい」という話は聞いていたが、「急流にオトリ鮎を泳がせかかれば一気に下流へ走る」という鮎釣りの昔ながらの醍醐味にこだわる私の性に合わないと思っている。「柳の下にいつもどじょうがいない」。これは釣り人に対する例えの様であり、未練がましいのが釣り人(私)の本性の様であろう。自分の考えた仮説(養殖鮎は釣れない)がありながら、ごくごくまれに「釣りでは(人生では)何が起きるかわからない」という反対の方を選んでしまう。「未練がましい根性」のうえにその根性が曲がっているのかもしれない。こういう人間は、そこでの多くの失敗を経験して、やっと気がつく。そして周りのみんな(釣り人)よりおくれて、浅野川を後にして犀川に釣り場を移した。この川は放流に加え天然遡上の鮎も混じり、型は小さいが、数はほどほどに釣れた。 ここ金沢で釣りを始めて一ヶ月ほども過つと、川の中での歩行も少しは慣れ(それでも、ころんであちこちにアザができた)身のほど知らずの大漁は期待せず、休憩して他人(ひと)の釣りを手本にしようと対岸からながめる事ができる余裕も出て来た。多くの釣り人は私のように定年を過ぎた様な齢(とし)の人達である。(若者は平日の朝から釣りなどできないでしょう)そのスタイルは皆、私より上等である。だが足元が、おぼつかないのは同じである。不思議な事に(当然とも言えるが)川の中でころんで立ち上った時に回りをキョロキョロ見わたす。たぶん「誰かにぶ様な所を見られたか」と。それを見た私は「何も見なかった」と横か下を向く。(釣り人の情け)たぶん家族がその光景を見ていたら、「そんな危ないマネをやめて」と言うだろう。「別に命がけでやっているつもりはない。齢(とし)だからといって少々の危ない事で、好きな事をやめてしまえば何もできない」「でもケガでもしたらどうするの」。これは私と我妻、子供達との長年の交わる事のない口論である。 午前中いっぱい釣りをして、昼食(おにぎり二個)は環状線が通る大きな橋の下でとる。そこは日陰になっており真夏でも少し風が通り、橋の下のコンクリートがひんやりとしていて気持ちがよい。いつの間にかうたた寝をしてしまう。横に釣り竿がなかったらホームレス(河原こじき)である。近所の子供に見られたら、「あのおじさん(おじいさん)、毎日一人で橋の下で寝てるよ」と言われそうだ。(私の子供の頃、村の近くを流れる川の橋の下に、今の私ぐらいの齢の人がいつも寝ていた)気持ちよく寝ころんでいると、大学生の頃の東北での鮎釣りの事を思い出す。放浪の果て(そんなカッコのいいものではなかった)持ち金もなくなり、やっとたどり着いた東北(岩手県)の親類の家で、まずメシを食わせてもらい、主人(当時六十代の医者)に「これからのお前の予定は」と聞かれ、「何もない」と言ったら、「俺と釣り(鮎釣り)をやろう」と言われた。それから一ヶ月間ほど毎日鮎釣りをやった。それが毎年夏の私の行事となり、三年間ほど続いた。 その医者は若い頃(東北大)は剣道に熱心で「御前試合」で天皇の前で試合を披露したそうである。私が出会った当時も道場で若者に剣道を教えていた。一度、私も「剣道をやるか」と言われたが、「いやです」と言ったら、それ切りだったので「ほっとした」事を覚えている。診察のあい間や診察後、患者に見られない様私が車を裏に回し、近くの川に直行する。彼は車から川岸に降り立つと、まず深呼吸して、大きな声で、「川はいいな」とさけび、釣り道具を持って川原に着くとまず自分の「ふんどし(越中)」を取り出し(ずぼんの中から器用に)、川でジャブジャブと洗い近くの小枝に干し、「よし始めるぞ」と言って釣りはじめた。そして夜は彼の言う「天守閣」(三階の自分の室で、女人禁制)でその日の釣りの話をし、仕掛けづくり、竿の手入れ等をするのが日課となっていた。 その彼が若い頃兵役で大陸に渡り、終戦になってシベリヤ(旧ソ連)に捕虜となって抑留され、将校(軍医)だったので最後まで日本に帰れず、つらい思いをしたらしい。(彼の奥さんから聞いた)二人でいつもの様に夜、彼の室で釣り道具の修理をしている時に、私としては深い考えもなく、「シベリヤ抑留」の話を切り出した。彼は急に顔をこわばらせ、「俺は自分が死ぬまで誰にもいっさいその事は話さない。自分一人で墓まで持っていく。戦争は人間が人間でなくなる」と。それ以後は私も戦争についての話はしなかった。「多くの戦争体験者が、彼の様に重くつらい荷を背負ったままで生きている。そしてそれらの人々の犠牲の上に現在の平和がある」と、その時自分が殊勝な気持ちになった事も覚えている。 ある年、金沢にいた私のもとに電話があり、彼が胃ガンでもう長くないという連絡だった。私がかけつけた時はもう意識もない状態であった。奥さんに聞いた話では、胃ガンと診断され、すぐ入院となったが、医者だから「もう助からない」と悟ったのか、「もう一度自分が長年釣りに通った川を見たい」と言って、車で連れていかれ、一人川原に立って、じっと川を見つめて涙ぐんでいたという。ふる里の川とはそういうものだろうか。私も若い頃はいろんな川に行き川釣りをやった。特に渓流釣り(イワナ、ヤマメ)では、「こんなすばらしい景色、空気感は絶対に写真なんかで現わせない。どんな庭師もこれ以上の景観はつくれまい」などとよく思っていた。ただ、今(この齢では)どの景色を見ても、それほどの感激はない様で、たぶん年取って感性がにぶくなったのだろう。原因は私の末端の神経がすり切れてしまったのだろう。感性がにぶるのはいやだけれど、その分、図々しくなり、生きやすくもなった。まあ今の自分で「よし」とするか。ただ私が「余命いくばくもない」と言われたら、最後にどの川へ行くだろうか。彼(医者)とちがって根ナシ草の様な生き方をしてきた自分には、「ふる里」などという感傷もない。ひょっとしたら、「自分の知らない所で死にたい」と言うかも知れない。まあ、その時になったらわかるだろう。鮎のように今年限りの命(鮎は一年だけの命)であるまいし。 たわむれに 野鮎のごとくに 生きんかと |
| 第七十回へ 第五十回特別編 詩「今」 |