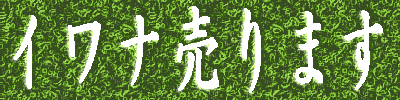 |
 |
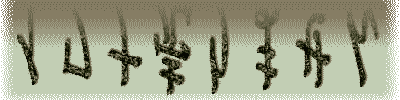 |
 |
| 河崎 徹 | |
| 河崎さんは、金沢近郊の医王山(いおうぜん)で、イワナやヤマメなどの養殖と、川魚料理の店「かわべ」をやっている、そろそろ落日間際の六十代。仕事より、魚釣りやら草野球やらにうつつを抜かし、店の方は、気が乗らないと勝手に閉めてしまうのが玉にキズ。(でも料理はウマイんだな)。いつもマイペース、ままよ気ままの行きあたりばったりエッセイからは、その人柄が伝わってきます。 |
|
| 第七十二回 「鮎釣りの話とヒトコト余計な一文(後篇)」 |
| 私が文章の中で「余計な事を書く」というのは、私の恩師、奥野良之助(故人)ゆずりであり、又それなくして私が文章を書く意義(楽しみ)がないので、少しちがった視点で(独断と偏見)でもって鮎の事を書いてみたい。奥野良之助の著書『生態学から見た人と社会』(創元社)をもじって「今の鮎の生態から見た人と社会」。 現代人は養殖鮎に似ている。(養殖鮎は現代人に似ている)私は鮎ではないけれど長年、人里はなれた渓流にしか棲まないと言われたイワナを自分で釣って、そこから養殖を始めた。 当時(40年ほど前)はまだイワナ養殖は他でもほとんどなされていなかった。イワナは「孤高の魚」「まぼろしの魚」と言われていた。それが今では私の養魚場では、「これがあのイワナ」と言われるくらい、飼育(養殖)しやすくなった。私に言わせれば、ダマされ、人間(私)にコントロールされるようになったイワナが変わったの? イワナの長い歴史のなかで、たかだか三、四十年ぐらいでDNAがそんなに変るものでもあるまい。(飼育されやすい(?)イワナだけが残った、という事も多少はあるだろうが)要は人間(私)の飼育(ダマし)の技術によるものと、イワナ(人間をも含む静物)の適応力(それがいいのか、悪いのかを度外視して)であろう。それは前記したように二つのポイント(イワナの発達段階における重要なポイント)を把握できるようになったという事だろう。実際には卵から孵って人工のエサを与え「これを食っていれば安心、これしかない」を覚えさせ、次にこれまた自然界のイワナでは考えられない密度のせまい池でも「この「池」は安心、ここしか生きる場所はない」と思い(?)込ませる事ができれば、ほぼ成功である。いや私がそうさせたというより、イワナ(生物)のもっている適応力の範囲を少し利用したといえるだろう。(結果)はっきり言ってしまえば、ある子供(稚魚)の時期に「お前の生きる道はこれだ(これしかない)と、思い(?)込ませ(すり込み)ば、その後はコントロールしやすいという事だろう。もっとも、そこには種(イワナ)が長い歴史を経て周囲(環境)に左右される最低(基本的)の条件(水、酸素……)は必要であり、さらに人間(私)の見た外見上は正常であろうと思っても、魚心はわからない。人間同様大きなストレスを負って生きているかもしれない。(私は時々「この池魚(イワナ)、エサを食うだけの生活で何の楽しみがあるのだろう」と思う事がある。でもそう思う時は人間(私)が同じ様な生き方をしていると思っている時である)。 さてここまで書いていて、私の文章を読んだ事のある人は、たぶん「余計な事」を書くための布石である事に気がつくでしょう。簡単に言ってしまえばイワナも人間も、大きな範囲内では「どの様にでもなる要素を持って生きている」という事である。いい意味でも、悪い意味でも、適応力を持って周囲(環境)の中で生きているという事であり、特に子供の頃の教育(育児)でコントロールされる。前記した私の恩師奥野さんが定年を機に書かれた、これまでの自分の人生の集大成の一冊『生態学から見た人と社会』の出だしが「内心忸怩」で始まり、社会にコントロールされた少年時代の話だった。「あの人(奥野さん)が立派な(?)軍国少年」と思ったが、別に珍らしい話ではなく、あの当時(戦争中)は当たり前の話で、私達の知る戦後の知識人、文化人と呼ばれた人の大多数はそうであった。ある意味での社会(環境)に対する適応力で、「何にでもなる」を発揮していたのである。 では今の時代はどうだろうか。「思想などアテにならない」と冷戦時代は終り、「やがて宗教、民族による紛争が起るだろう」の予言通り、子供の頃から何の疑いもなく「すり込まれた」民族意識、宗教で世界は紛争だらけであり、先進国(日本も)の子供の頃からの競争原理の資本主義も格差社会と言われ、流しそうめんのごとく、下流の人達にはいつまでも流れてこないそうめん(金)にみんな「いらいら」している。では「そういう中(社会)で生きているお前はどうなんだ」と言われそうだが、周囲から(子供の頃から)養殖鮎(養殖イワナ)の様に育てられ、ハタ、と気づいて、もう何十年。野鮎の様に周囲の鮎をけ散らして、カッコよく生きたいけれど、過去の養殖ぐせが身についていて、「人間は一人では生きられない」というありふれた言葉の中、今も私は「内心忸怩」たる思いで生きている。奥野さんもあの本の最後に「内心忸怩に始まった話がまた内心忸怩にもどってきたこのあたりでおしまいにしましょう」としめくくっているし、やはり本の中で、人間(特にエライ人)は「内心忸怩」で生きていくのが丁度いいと言っている。まあ、人間は(他の生物はいざ知らず)過去をふり返る事ができる生き物である。よからぬ教育(飼育)で、よからぬ適応力を発揮した戦争も「過去のあやまち」とされている。だが今頃ではまた指導者は自信気に「人間(生物)は何とでもなる」を利用して都合のよい様にコントロールしようとしている。私が奥野さんに最初に会った時、聞かされた言葉は「ぼくが敗戦の経験で学んだ事は、エライ人の言う事はまず疑ってかかれ」だった。その言葉が今私には「やたらと新鮮な言葉」に思えてくるのである。 亡き人を ふと想う事あり 秋の暮れ |
| 第七十一回へ 第五十回特別編 詩「今」 |