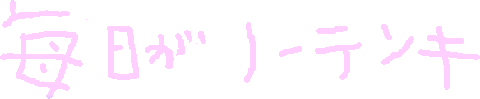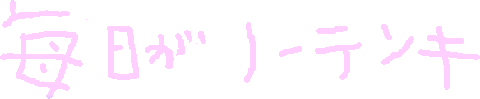|
実は、わたしには父の思い出があまりない。
わたしは“完全無欠のおかあさん子”だったからだ。姉との二人姉妹。妹のわたしは6年生になっても、母が正座をしていると、その膝のうえにヒョイとまたがってしまうような甘えん坊だった。わたしの視界にはいつも母の姿があり、この世の中に母さえ生きていてくれればそれでいい、というような子どもだった。わたしにとって、父の影はあまりにも少なかった。
でも、父のことで妙に覚えていることがひとつだけある。
それは夕飯の記憶。もう30年以上も前の、わたしが小学生のこと。
その当時はテレビは一家に一台というのが普通の時代で、テレビを囲むように4人が座卓に座って、小学生のわたしなどは食い入るようにテレビを見つめながら夕ご飯を食べていた。ちょっと行儀が悪いが、それでもそのころはテレビがようやく各家庭に根付き、世の中の高度成長に伴ってテレビ番組も活気を呈し、まさにTV黄金時代。それが当時の正統な「家族の夕餉(ゆうげ)」だったように思う。
銀行マンだった父は月末などは帰りが遅くなるのだが、だいたいは夜の7時ぐらいに帰ってくるのが決まりだった。実はわたしは、父と食べる夕飯があまり好きではなかった。
なぜなら父がいると7時から始まるマンガが見せてもらえず、NHKのニュースにチャンネルが回されてしまうからだ。わたしは、特に好きなマンガがある日は、どうか父が残業で遅くなりますように…と、心のなかで祈った。夏など、プロ野球がある日はなおさらだった。ニュースが終わると野球のチャンネルに自然に回されて、その日のテレビはもう父の貸切状態になってしまった。
特別な亭主関白、雷親父、厳しい父ということはなかったけれど、テレビが一家に一台のその時代は、父の威厳がまだまだ生きている時代だった。
そうそう、書きたかったのは、父の夕餉の記憶。
そんな「一家で一番エライ」父だったが、なぜか我が家の場合、夕飯が終わってちゃぶ台の上を拭くのは父の仕事だった。
食べ終わると、姉とわたしとでみんなのご飯茶碗やみそ汁の椀を「ごちそうさまぁ」と言いながら台所の流しまで下げるのが日課だった。母は洗い場に積み上げられたお茶碗を早速に洗いはじめるのだが、父はお皿を下げることもせず、座ったまま。でも父は、正座していた足をくずし、あぐらの格好に座り直しながら、ショーユやおかずの汁がこぼれたちゃぶ台をそこに置いてある台拭きでいつもきれいに拭いてくれた。
その時の方法がちょっと変わっていた。急須に残っているお茶や湯呑みに残っているお茶をちゃぶ台の上に派手に振りまいてから拭くのだ。それが父の決まったやり方だった。お茶で潤し、こびりついた汚れを一掃してしまおうという方法だ。
父の記憶はまったく少ないのに、この横着かつ豪快なやり方で座卓をキレイにする父の姿が、妙にわたしの幼い記憶のなかに貼りついている。
結婚して、家族を持ち、今はもう父とは暮らしていないが、わたしも時々父のやり方でテーブルを拭く。そんなとき、なぜだか心がほわんとあたたかくなる。きっと、世の中の苦労をなにも知らずに生きていたあのころのぬくぬくとした感覚が、知らず知らずのうちによみがえってくるからかもしれない。
父は今、老人性の目の病のために入院中だ。忙しさにまぎれて足繁くはお見舞いに通ってあげられないが、たまに行くと父はすまなそうな顔をして、「ありがとう」を何度も言う。ひととき話をして、洗濯物をもらって、慌ただしく病院を出るのだが、いつも父は一緒にエレベーターで降り、1階のエントランスまで来てくれる。「危ないから、いいよ」と言うのにきかない。
父は見えない視界でいつまでもわたしを見送ってくれる。わたしは何度も振り返りながら、きっと、ちゃぶ台を拭いていた父の姿と同じくらい、病院の入口にポツンと立つ、ひとまわり小さくなった父の姿が記憶に焼きつくんだろうなあと思う。

父はいつもお茶でちゃぶ台を拭いてくれた |