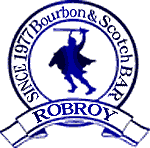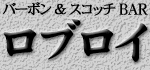MAKIKO・こんどう
クリスマスも近づいたある日、いつもは無口なバーテンダーが、今夜はどういう訳だろう、自分から口をひらいた。
「今年限りでこの店を辞めるんです」
「ああ、そうなんだ」
僕はてっきり、彼は腕のいいバーテンダーだから、どこか別の店に引き抜かれでもしたんだろ、と思い、
実にあっさりと答えてしまった。珍しく彼は話を続けた。
「あの、就職が決まったのです」
彼に初めて会ったのは東京から移り住んでまもなくの事だ。まだ宵の口だというのに、
明かりのまばらになった町を、バーを探して歩いているときに、駅前にホテルがあることを思い出した。
案の定、最上階にはバーがあるらしい。エレベーターを降りると、ちょっと驚いてしまった。
この町には不似合いなほどに、落ち着いた、小綺麗なバーだったからだ。
カウンターに通された僕は、いつものようにバーボンを注文した。
「グランダッドですね・・・、かしこまりました」
バーテンダーは丁寧に注文を聞き直すと、慣れた手つきでグラスの中の氷を回し始めた。
2杯、3杯とグラスを重ねながら、いつしか僕は彼の仕事の丁寧さにすっかり感心させられていたのだ。
おかわりを作る、灰皿を取り替える、チェイサーを注ぎ足す・・・。
贅沢ではあるが、バーテンダーは全ての客に対して、こうでなくてはならない。
しかし、みなそれぞれタイミングが違う訳だから・・・と思うのだが、バーテンダーという人種は実に記憶力が良い。
バーテンダーとは、ただ酒を作り、注ぐ仕事ではない。客のくつろげる空間をいかに演出できるかが勝負なのである。
より多くの「タイミング」を記憶できない人にバーテンダーは務まらない。僕よりは、きっと幾つも若いのだろう。
まだあどけなさの残る笑顔と、どことなく漂う品の良さが、妙に印象に残る青年だった。
「お待たせしました」
2杯目のおかわりが言いもしないのに出てくる。いや、これでいいのだ。
彼は私の「タイミング」をすべて知っているのだ。この若干23歳の青年は、バーテンダーとしての基本を見事にこなしていた。
「・・・・・・どうしました?」
しばし思い出を巡っていたところ・・・いや、もしかしたら目が宙を泳いでいたのかもしれない。
少々はにかみながら先程の会話を続けることにした。
「今度は、どこのなの?」
すっかりバーテンダーとして就職することが決まったのだと思いこんでいた私に返ってきた彼の言葉は意外なものだった。
「いや・・製薬会社なんです」
「!?・・・製薬会社???バーテンダー、辞めちゃうの?」
「そうなんです」
酒が好きで、あれ程バーテンダーという職業が好きだと熱っぽく語っていた彼が、いったい、どうしたというのだろう。
聞けば、バーテンダーとして生涯を送ることに、ご両親は猛反対なのだそうだ。
彼自身も、それに押し切られたような形になってしまい、一度は社会を見ることも悪くはないと思い直し、
大学卒業を期に、就職する事にしたのだそうだ。一瞬、女にフラれた訳でもないのに、なんだか酒が苦くなったような気がした。
帰り道、彼が、いつかはまたこの仕事に戻りたいのですとしきりに語っていたのが気になった。
以前、彼に名刺を貰ったことがあるのを思い出した。咄嗟に取り出し、携帯電話のボタンを押した。
「少々お待ちください」
保留音が流れている間、僕はひどく後悔していた。忙しいところを呼び出すなんて失礼だし、やめるなよ、と言うのも唐突だ。
かといってこのまま切るのはもっと失礼だ。おまけに自分の名前を告げてある。
「お待たせしました」
彼だ。随分と時間がかかった。きっと忙しかったのだろう。アタマの中がパニックになっていた僕はあわてて彼にこう言った。
「辞めちゃう前に一度飲みにいこうよ。僕の知ってるバーテンダーでS田って奴がいるんだ。きっと イイ話が聞けると思うよ」
「ありがとうございます。是非ご一緒させてください」
僕は携帯の番号を教えるとそそくさと電話を切った。就職してもがんばってと言いたかった・・・
いや、本当は辞めるなよと説得したかったのに、自分一人の力で彼にものを言う勇気がなかった。
結局、S田をダシにするしかなかった自分が情けない・・・・・。
S田の店は某郊外の大きな町にあった。駅で待ち合わせした僕らは、早速、店に向かった。
もちろん、彼が来ることはあらかじめ連絡してあった。
S田の店の雰囲気や客層は、ホテルのバーとは明らかに違う。年齢層は若いし、幾分カジュアルな感じだ。
2人でカウンターに陣取る。バーテンダーと真っ正面に向き合うこの席に座れるのは、ちょっとした常連の強みなのだ。
バーテンダーと話も出来るし、注文も出しやすい。S田はわざわざこの席を空けて待っていてくれたのだ。
何からしゃべってよいのかわからない僕。そんな僕にS田が気を利かせる。
「いらっしゃい。こちらが彼ッスか?」
「宜しく」
初めてこの店にきた彼のほうが、なんだか堂々としている。彼を紹介しそびれた僕は、なんとなくバツが悪かった。
しばらくして、S田と彼は酒の話で盛り上がっていた。さすがは専門職同士、その会話の内容は僕にはよくわからない。
ピーナッツをもくもくと食べながら、バーボンをすすり、しばし彼らに見入っていた。
こうしていると、二人は実に対照的だ。バーテンダーとしての基本はどちらも申し分ないのだが、
S田はいかにも町のバーテンダーといった感じなのに対して、彼はいかにも品のいいホテルのバーテンダーといった感じだ。
(別にS田に品がないと言う訳ではないが。)
話を聞いてみると、「社会人としての心構え」という点ではまだまだ若いなと思わされる。それは僕が彼よりも年上のせいだ。
言いたいことも言えないまま、終電の時間が近づいていた。
まだるっこしい自分にホトホト嫌気がさしていたその時、S田が彼にこう言った。
「バーテンダーやりたいなら、またいつでもやれるよ。30になっても40になっても一度覚えた基本は忘れること無いよ」
彼の顔が、パッと明るくなった。そして、何度も何度も確かめるように言った。
「そうですよね。いつでも・・・、いつでも戻ってこれますよね!!」
しばらくして、彼から一枚のハガキが届いた。在職中(?)はお世話になりました、と書いてある。
アルバイトに在職中もないもんだと思い、それでもなんだか生真面目で彼らしいな、と読み進むと最後に
「PS」と付け加えてあった。
”P・S.いただいた名刺、大事にします。バーテンダー復帰の際は真っ先にご連絡いたします”
それからというもの、彼のいたあのホテルのバーにも何回かは足を運んだ。代わりのバーテンダーが入っていたのだが、
彼のいないバーは楽しくも何ともなくなってしまった。最後に行ったのは、一体いつだっただろう。
あそこには、もう僕の「タイミング」を知っている人はいないのだ。
今でも時々彼にもらった名刺を取り出して見ては、自分と同じ営業マンという職業についた彼はどうしているのだろうと思う。
そして、彼のいたバーに行かなくなった代わりに、彼から電話がかかってくるのは何年後だろう、そのころにはひょっとして、
僕は身体を壊していて酒が飲めなかったら困るな、とか、くだらない事を考えている時間が、新しく僕にはできた。