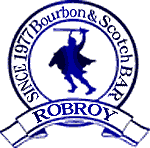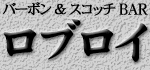先日、小さい小さいカタツムリが死んだ。
飼っていたわりにはカタツムリの事は何にも知らない。
「カタツムリが死んだ」と書いたが、実際死ぬところを、たとえば犬とかネコのように腕の中で眠るようにとか、
病気で、又事故で死んだ訳でもなく、ある日気が付いたら動いてはいなかった。
という言い方が最も当てはまるような気がする。いつ死んだのかさえ分からない。
今から四年前のある日、居間のテーブルの上にビンの底直径十センチくらい、
縦十五センチくらいの丸い透明のビンが置いてあった。その中に無造作にちぎった白菜が入っている。
広口のビンにはストッキングを切り取ったらしい物で口を止めてある。当然何らかの昆虫でも入れているのだろうと思い見てみる。
しかし上から見て、横から、またビンの底から覗いて見るのだが、それらしい物は何も見えない。
隣のキッチンで洗い物をしていた嫁さんに「コレは何だ」と聞いてみると「カタツムリが入っているでしょう」と言う。
僕は「何も見えない」と言うと、ビンのある一点を指差し「ほら、ココに」と言う。
よく見ると確かに薄茶色の粒らしきものがあり、僕はルーペを持ち出し覗いてみると、小さい小さいカタツムリが居た。
殻の大きさが一ミリくらい、尻尾からあたま(触覚)まで入れても二ミリあるかないかである。
老眼の始まった僕にはなるほど見えないはずだ。カタツムリの子(?)がこんなに小さいとは知らなかった。
(通りすがりの草むらに居たとしても気が付かないだろう)とりあえずどうしたのかと聞くと、
当時小学生の娘が入浴中窓ガラスで見つけたとの事だった。
少しは知識を得ようと思い、娘の部屋から昆虫図鑑を持ち出し、見てみるがいくら探してもカタツムリは載っていない。
後で分かった事だが載っている筈がない。カタツムリは貝(陸貝)であり昆虫ではない。
(ついでにナメクジは殻を持たない貝だそうである。)
よく分からないまま白菜の他にキャベツ、レタスなどをやっていたが、その中ではレタスを良く好んだ(?)ように思う。
それから何日か経ち<ロブロイストの日々>も書いてくれた貝の収集家「森川氏」が飲みに来たので、早速聞いてみた。
まず『餌は香りの強いものを好み、あまり大きくなる種類の物ではない、寿命は多分三年くらいだろう』と言う事だった。
次の日、日当たりのいい窓際においてあった。大き目のレタス二枚の上部を離し(いわば逆ハの字に)置いてある。
その一枚の一番上で、もちろんガラス瓶越しであるが彼(?)は窓の外を見ていた。
僕は手短に香りの強い、というとキュウリかなと思い、より青い所を一枚スライスして、彼の座って(?)いる反対側(もう一枚)のレタスの上にちょこんと乗っけてみた。
すると右回りに首をキュウリの方を向き「フムッ、こ、これは」と言ったかどうか、ともかく反応が早かった。
しばらくして今度は首を左側にぐっぐっぐっと廻し、僕の方を見ると、
「やっとオレの好みに気が付いたか、このバカ飼い主が」
と言ったような気がした。
そして彼は「まあええわい」と言いたげに下を向き、あまり急いで餌の方へ行くと軽くみられると思ったのか、
落ち着いた足取り(?)でゆっくりズリ、ズリッと動き出した。(といっても急いでいる所を見た事はないが)
ところがである。殻一ミリの彼の世界を頭に描いて欲しい。十センチは彼にすると大変な高さになる。
人に置き換えると<身長の百倍の高さ>という事になる。人が170センチとしても170メートルの崖を谷まで降り、
また頂上まで上がらなければいけない訳である。ましてレタスの葉の形状からして平坦ではない。
一ミリの彼にとっては大変な道のり(登山)という事になろう。(ザマーみろ?)と言いたいのは先に
「バカ飼い主が」と言われたので、ちょっと腹が立ったのである。(カタツムリと張り合っている)
ともかく彼は、ゆっくりと谷へ向かって進みだした。相変わらず僕はルーペを通して見ていたが、
一時間に三センチは進んだだろうか、このスピードでは後どのぐらいかかるか分からないので僕はその場を離れた。
四〜五時間後にそ〜と覗いて見ると、キュウリにへばり付いている。どうやら夢中で食べているようだ。
コレもあとで知った事だが、ちゃんと目もあり、ヤスリ状の歯があり、削り取るようにして食べるらしい。
それからのレタスは岩、もしくは日よけ代わり。食事はキュウリとなり、たまにルーペで覗くと
「フン・・・」という感じではあったが、その年の秋には倍ぐらいの大きさ(倍といっても二ミリだが)になった。
冬は一種の冬眠状態になるらしく、一切動かない。明けて春になり、キュウリはもちろんだが、
殻のためにカルシウムも必要だろうと思い卵のカラなども置いた。
その年には三ミリぐらいになり、なんとか裸眼で見れるようになった。
日当たりのいいところに置き、僕は横になり見ているとふと、あの「フン・・・」という感じがなくなっているような気がした。
僕に気付いたように見えても、特に不自然な動きをしなくなった。
年は明けて先月の事である。彼を見てみようとするとアレッと、思った。なんだか僕が彼を見る前に、
彼が僕を見ているような気がしたからだ。彼を見ながら僕は「何だかヘンなもんだなあ、うんヘンなもんだ」と、
心の中で呟いていた。
今月になった。小さな、小さな彼は死んでいた。